しょうろんろん!(入試はつらいぜ、の巻)
- カテゴリ:日記
- 2013/10/01 21:39:34
現代社会は、超高齢化社会、長寿社会、高福祉社会といわれている。
神社においても加齢によって弱者となる氏子、崇敬者が増え、これらの信者を支援する対応が一部でみられる。
その対応の一つとしてバリアフリー化があげられるが、神社でのバリアフリー化には神社の聖構造が変化し、聖域が俗化してしまわないか、また、バリアフリーを実施する上での経費や、景観が損なわれないか、などの困難な問題が複数存在し、実施を容易にできないという葛藤も生じている。
日本がますます高齢化していき、高齢者や弱者の参拝が常態化したときに、変化に応じて神道界もその影響を受けざるを得ない。その中で、神道人からは「不易と流行」という言葉が聞こえてくる。
何を代えてはならないか、変えても良いことはなにかを厳しく吟味し、バリアフリーによって神社の空間構造や神社参拝がどのように変化していくか、今後も引き続き関心を持ちたい、と筆者は述べている。
以上が松井志眞秀氏の「バリアフリー化と神社」の要旨である。
これらを踏まえ、神社の空間構造の変化、空間の保護、具体的なバリアフリーの実施方法、の3つの点から私の考えを述べていきたい。
まず、神社の空間構造の変化についてだが、本論文で述べられているように神社には俗なる人間が、聖なる神に近づくための浄化のステップというものがある。
このステップを順次辿ることにより、浄化が高まっていくこととなるのだが、浄化の際に必要とされる階段や神へ近づくまでの高低差が、高齢者や障害者などの弱者にとってバリアとなりうる。以下、車椅子使用者をはじめ参拝弱者が神社参拝を出来ることをバリアフリー参拝と略称するが、このバリアフリー参拝を実施するにあたって先ほどのバリアとなりうるものを普通の公共施設のように撤去することは神社の伝統的な構造を守ることや、宗教的意義のある構造は無くせない等の理由で勿論出来ない。
では、完全に撤去するのではなく、伝統的な構造である階段と、バリアフリー参拝のためのスロープ、この二つを両立することは可能だろうか、という考えに至ったとき、もう一つの神社の景観、という問題が浮上してくる。
神社とは神を祀る、ということ以外に古くからの伝統や構造様式などを今に伝える大切な役割を持つ文化財でもある。
神社内の空間を現在だけでなく未来にまで残す、と考えたとき、現代の理由で今まで守られてきた景観を崩してもいいのだろうか。
この問いについて一つの例を挙げてみたい。
宗教は違うが、私の知人で世界遺産に登録されている大きな寺院で僧職を行っている人がいる。
その寺院でも高齢者や、身体障害者の方が多く参拝に訪れるのだが、その方々に配慮し、手すりやスロープをつけようとすると文化庁などの行政から注意を受ける事があるそうだ。ちょっとした手すりをつけるだけでも申請が通るのに半年以上かかることも少なくはないとの事である。そのときに文化庁からは何時も「現状維持」という言葉を繰り返されると言う。
文化庁の言う「現状維持」とは昔から守られてきた文化財を現代の都合で変えないようにという事だろう。勿論これは同じ宗教的施設で文化財でもある神社などにも当てはまる。だが、文化庁の言うように現状維持だけを続けるわけには行かなくなっている実状がある。
事実、消防法などによって、神社仏閣などの宗教施設にもスプリンクラーや放水銃なども設置が義務付けられるなど、バリアフリーだけでない神社自体の変化も求められている。
対応を迫られた神社の中では、問題に戸惑う神社もあれば、うまく工夫し、具体的に実施している神社もある。
私の住む地域のとある神社では拝殿の前にある階段のすぐ側にスロープが設置されている。そのスロープはゆるやかで、手すりはないが、材質が階段と同じよう石で出来ており、一見してまったく違和感はない。また、スロープのすぐ脇には社務所があり屋根のおかげで雨の日は濡れないばかりか、車椅子の方が参拝に来られたらすぐに手助けができるようになっている。
もし、手すりをつけたりスロープを違う材質で作っていたらここまでの自然さは感じられないと私は思う。
その他に香川県にある金刀比羅宮といえば長い階段があることで有名だが、そこではお金を払うと籠にのせて上まで運んでくれるというシステムがある。
このように神社の空間構造は、歴史的経緯や風土の問題もあり、きわめて多様で一環とした対策はたてにくいものの、それぞれの神社の構造を生かしてバリアフリーを行っている神社は沢山ある。
そこで何を変えてはならないか、変えても良いか、聖域が俗化してしまわないか、などに注意を払いバリアフリーを実施することによってこれからますます変化していく現代社会の中でも、神社というものが現状を維持するだけでなく、社会に対応できる新しい宗教のあり方を生み出すことが出来るのではないだろうか。また、日本人の心に深く根付く神道という宗教だからこそ、現代日本に上手く対応していけるのかもしれないし、これが経典や明確な教えを持たないが故に常に変化していくことの出来る神道の本来の姿なのかもしれない。
みたいなことをていしゅつするつもり!


















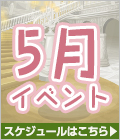







流石じゅのたんだわね、綺麗に纏まっててすげえや!!←
あたくし考えるのは好きだけど構成が苦手なのでした
頑張ってくれええええええ