28日おしゃべり展望 構造色
- カテゴリ:タウン
- 2019/06/28 08:01:09
仮想タウンでキラキラを集めました。
2019/06/28

| 集めた場所 | 個数 |
|---|---|
| おしゃべり広場 | 7 |
| 展望広場 | 15 |
モルフォ蝶やCDの煌めく色は構造色と言って、光の波長と同じくらいの大きさの凸凹があることで、 反射される色、吸収される色が決まります。本体に色素があるわけではないので色褪せしない理由です。 そのような小さな凸凹をアクリル樹脂に作る技術を開発することに成功だそうです。 半導体を作る技術と同じ仕組みですね。 おまけ。世界一黒い フウチョウは羽の構造で殆どの光を吸収(98%)していると、ダーウィンが来たで放送してました。これも構造色です。
ーーーーー以下引用
アクリル樹脂などに代表されるポリマーに規則的に亀裂を入れることで発色させる新たな印刷技術を開発したと、京都大物質-細胞統合システム拠点(iCeMS、アイセムス)のシバニア・イーサン教授(化学工学)らの研究グループが、20日付の英科学誌「ネイチャー」電子版に発表した。
亀裂自体が模倣されにくく、高精密な印刷が可能で、紙幣や身分証明書の偽造防止印刷などへの応用が期待できるという。 コガネムシの体表などにみられる鮮やかな色は「構造色」と呼ばれ、色素を使わない特殊な構造が光を反射して発色する。
研究グループはこの構造色に着目。ポリマーに、特定の色の光を反射する微少で規則性のある亀裂を生じさせることで、全ての可視光を発色させることに成功した。亀裂は、ポリマーにLEDなどの光を照射し、溶剤で現像することで形成できる。発色する色は亀裂の規則性で決まり、亀裂の数が多いほどより鮮やかに見えるという。高解像度の印刷にも対応し、グループはこの技術を用いた約1ミリ四方の絵画をフルカラーで描くことにも成功した。
インクを使わないので、退色のおそれがない。また、製作時間も短く、特別な材料や設備を必要としないため、従来より安価で大規模な高精密印刷が可能になるという。グループの伊藤真陽特定助教は「物質を破壊して色を表現することに、世界で初めて成功した。産業界に大きなインパクトを与えられるのでは」と話した。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/20/news064.html 引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1561025984/





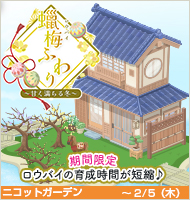





















コントロールディバイスは組み込まれていないので、
構造色印刷(露光、現像(溶剤で溶かす))レベルですね。