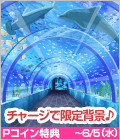耳鳴りの向こうに
- カテゴリ:自作小説
- 2020/12/25 14:08:36
「あのね。家があるのに、いない動物ってな~~んだ?」
娘の真美は、あどけない笑顔で、私の目を覗き込むようにして、なぞなぞを問いかけてきた。
「なんだろうね。降参。」と、私は、娘の相手をするのが面倒くさくて、考えようともせず、新聞から目もそらさず、すぐに答えた。
娘の真美は、「ふ~~ん」と笑顔から急に真顔に戻り、声が少しとがった感じになり、「ママにこのなぞなぞ出したら、ママはね。答えは、パパっていってたよ。」
「ジージー、ジージー」右の耳から耳鳴りがする。
まるで、耳の中にセミを飼っているかのようだ。
いつごろからだろうか、最初は気のせいだろうかと思っていたが、いまでは、耳鳴りのせいで、夜も寝れないほどだ。
耳鳴りが始まると、右手で頭の右の耳の上あたりを叩く癖がついてしまい、
電車の中でも、会社でも無意識にどこでもやるので、周りの人の視線が気になるようになってきた。
病院に行っても、耳鼻科の背の小さい年老いた医者は、「加齢のせいでしょう。ストレスを避けてゆっくりしてください。」と、慰めにも似たようなことしか言わなかった。
「直らないと言うことですか?」と、私が聞くと、医者は「病気は、直すのではなく、うまく付き合った方がいいということです。神様が少し休みなさいっていってるんですよ。」と、今度は、しっかりと慰めた。
自宅で、TVを見ている時だった。
まただ、「ジージージージー」と、耳鳴りが始まった。
いつもの癖で、右手で右の側頭部を叩くと、一瞬、耳鳴りが止まった。
すると、耳の奥の方から、何かが聞こえてきた。
TVを消して、その音に集中すると、人の声のようにも聞こえた。
息を止めて、目を閉じて、わずかな音を探っていると、女性の声のようだった。
「あなた、いつも仕事仕事って、言い訳ばっかり。」
「家族の事なんて、ほったらかしで、あたし、これじゃ、まるで、シングルマザーと同じだわ。」
一年前に、私に、愛想をつかして、真美を連れて実家に出て行った妻の恵美のあの時の声だった。
「何もかも、家の事、真美の事、全部、あたしに押し付けて、あたしは、あなたにとって何なの。お母さん?それとも、お手伝いさんなの?」
10年間、心の奥のダムに積もりに積もった私に対する、不平不満が怒りとなって、そのダムが決壊でもしたかのように次から次と溢れ出てきた。
「ねえ。何で何にも言わないのよ!」
恵美は、あの時と同じように、私が何か話しだすのを、怒りを堪えて待ち続けた。
「恵美なのか?」私は、恐る恐る、声に出して聞いてみた。
恵美は、はっと息を飲むかのように、凍り付いたように押し黙った。
そして、「ジージージー」と、また耳鳴りが始まった。
不思議と、恵美が私の耳の奥で、ヒステリー気味に私の事をなじりだすと耳鳴りは止んだ。一方的に、あの時のまま、私を責める言葉ばかりだったが、私は、あの時と違い、その恵美の言葉に耳を傾けた。
「私が、いつもどんな気持ちで暮らしているか、考えたことあるの?」
「いるのに、いない人を待ってる妻の気持ちがわかる?」
私は、一方的に、ただ聞くだけだったが、それでも、妻の声が聞けて嬉しかった。
「真美は、そこにいるの?」私は、娘の真美の声が聞きたくて、耳の奥に住み付いた妻に声を出して聞いてみた。
電車内の、見知らぬ若い女性が、薄気味悪そうに、私を見つめた。
私は、妻や娘の声が聴きたくて、耳鳴りの、向こうをいつも探っていた。
『いるのにいない人を、いつも、待ってる』のは、妻の方じゃなくて、私になっていた。
耳鼻科の医者に、この話をすると、心療内科を紹介された。
心療内科の医者は、年配のちょっと小太りの銀縁メガネをかけた笑顔の似合う女性だった。
その女医は、私の話を、「それで」「そうそう」「それから」と歌の合いの手でも入れるかのように、隅々まで、私の話を興味深そうに聞いてくれた。
「それで、どうするの?」女医は聞いた。
私は「どうするのって・・・・。幻聴をなおしたいんですが・・・」と、言うと
「そうじゃなくて、奥さんや、娘さんのことよ。」女医さんは、呆れたように言った。
私は、耳鳴りの向こうにいる妻と娘ではなく、現実の妻と娘の声を聴くため電話をかけた。
妻が電話の出ると「あの、田代ですが・・・・。」と場違いなことを言うと、妻が「あら、あたしもまだ、田代ですけど・・・・」と笑った。
「明日、車で向かいに行くよ。戻って来てくれるか?」私は、大きく深呼吸してから言った。「僕からの2回目のプロポーズだよ。やり直してくれないか」
「また、家政婦が欲しくなったの?」妻は、それでも嬉しそうに意地悪を言った。
「そう、いじめるなよ。俺が悪かったよ。明日、義父さん義母さんの前でちゃんと謝るから。」
「真美に代わるね。」妻の横に娘の真美がべったりくっついて、電話の様子を伺っているのが分かった。
「もしもし、パパ?」
「仲直りできたね。ちゃんと謝らないとだめだよ。」
「明日、待ってるからね。ちゃんと迎えに来てよ。」6歳のくせに、親の機微を敏感に感じて明るくふるまっているのが感じられた。
「あのなぞなぞなんだけど、・・・家があるのにいない動物ってやつ。」大切な話でもあるかのように私は話を切り出した。
「なぁ~~んだ?」真美がおどけたように言った。
「カラス、・・・空の巣だから。」私は、涙声で言った。
「ピンポ~~ン、あたりぃ~~~~。」真美は、幸せそうに笑った。
いつの間にか、耳鳴りが全く消えていた。
おそらく、耳鳴りの向こうにいる妻の恵美も、もう二度と現れることはないだろう。
汚くなった家を明日までに掃除しなくては。
「大変だ。」「がんばるぞ」私は、台所のシンクに溜まった食器を鼻歌交じりに洗いだした。
おわり