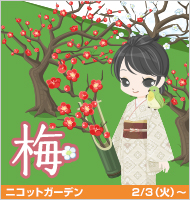進歩派知識人の雑誌「世界」 北朝鮮へのシンパシー
- カテゴリ:ニュース
- 2025/08/26 00:53:02
日本における進歩派知識人の論壇・雑誌「世界」はなぜ北朝鮮に友好的だったのか (朝鮮日報日本語版)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b40d4ca9ef7cb0d6b4598d27be782d4cfa86edea
戦後日本の進歩派知識人の思想と変遷:北朝鮮問題からマイノリティ運動へ
1. はじめに
戦後日本の進歩派知識人は、反権力・反米の思想を背景に、北朝鮮へのシンパシーを抱いてきました。本稿は、その思想がいかに現実と乖離し、拉致問題発覚後に新たな社会問題へとシフトしたかを分析します。
2. 北朝鮮へのシンパシーと現実認識の乖離
戦後の進歩派知識人の思想的基盤は、戦前の軍国主義や帝国主義への反省から形成されました。彼らは国家権力、特に米国を中心とする西側資本主義を強く批判し、「反権力」と「反米」を重要な柱としました。このイデオロギーは、北朝鮮へのシンパシーを生み出す土壌となりました。
・反権力・反米のイデオロギー: 進歩派は、冷戦下で米国を「帝国主義の象徴」と見なし、これに対抗する北朝鮮を「抑圧された側の象徴」として理想化しました。この単純な善悪二元論は、北朝鮮の体制を客観的に評価する妨げとなりました。
・共産主義へのシンパシー: 当時の進歩派は、社会主義や共産主義を資本主義に代わる理想的な選択肢として捉える傾向がありました。北朝鮮の「主体思想」や反米姿勢は、この思想的枠組みに合致し、魅力的に映りました。
・「地上の楽園」イメージの受容: 雑誌『世界』などのメディアは、北朝鮮のプロパガンダである「地上の楽園」というイメージを一部受け入れました。彼らは、在日朝鮮人帰国事業を「地上の楽園への安着」と肯定的に報じるなど、北朝鮮の社会主義政策を積極的に描写しました。
・現実の抑圧・人権問題の軽視: このようなイデオロギー的共感は、客観的な事実確認を上回りました。進歩派は、北朝鮮の独裁体制、強制収容所、飢餓といった現実を軽視し、自らの理想化したイメージに固執しました。
・ダブルスタンダードと選択的視野: 進歩派は、韓国や米国に対しては厳しい批判を展開する一方、北朝鮮や中国に対しては寛容な態度を取りました。これは「敵の敵は味方」という心理が働いた結果であり、北朝鮮の核開発や人権侵害を軽視し、米国の責任を強調する論調に典型的に表れています。
3. 拉致問題の衝撃と進歩派の失墜
北朝鮮の日本人拉致疑惑が浮上した1970年代から1980年代にかけて、進歩派や日本社会党は、これを「捏造された反北朝鮮プロパガンダ」とみなし、問題の存在を否定する立場を取りました。
・拉致問題の否定と軽視: 彼らは拉致問題を正面から取り上げることを避けました。疑惑自体を否定するか、軽視する姿勢は、イデオロギー的信条を優先した結果でした。
・家族会への冷淡な態度: 拉致被害者の家族や支援団体は、拉致問題を否定する日本社会党や一部の進歩派知識人から批判を受けました。
・金正日による拉致認定の衝撃: 2002年の小泉純一郎首相訪朝時、金正日総書記が拉致の事実を公式に認め、謝罪しました。この事実は、「拉致は存在しない」と主張してきた彼らの立場を根底から覆し、信頼性を大きく損なうこととなりました。
・左派の失墜と影響力の低下: 拉致問題における誤った対応は、日本社会党の衰退を加速させる一因となりました。国民の不信を招き、特に拉致被害者家族への冷淡な態度は世論の強い反発を招きました。
・イデオロギーの限界の露呈: 金正日の拉致認定は、進歩派が長年にわたり、イデオロギーのために現実を無視してきたことを露呈する象徴的な出来事でした。彼らの「見たいものだけを見る」姿勢が、いかに現実と乖離していたかを示す決定的な瞬間となりました。
4. 思想的エネルギーのシフト:新たな闘争の場へ
拉致問題の発覚は、進歩派にとって北朝鮮へのシンパシーを維持することを困難にしました。その結果、反権力・反保守の精神的支柱は、他の対象へとシフトしました。その主要な受け皿は、韓国問題、在日米軍基地問題、そして国内のマイノリティ運動です。
4.1. 韓国問題:歴史的正義の訴求
・「過去の清算」理念との合致: 慰安婦問題や徴用工問題は、戦前の日本の植民地支配や人権侵害と直結し、進歩派の「過去の清算」理念に合致しました。韓国側の主張を支持することで、進歩派は再び「歴史的正義の側」に立つ自己認識を強化することができました。
・国際的な人権運動との連帯: これらの問題は、グローバルな人権運動と結びつき、進歩派の国際的正義感を支えました。社民党などは、韓国側を「被害者」として支援することで、反権力運動をグローバルな文脈に拡張しました。
4.2. 在日米軍基地問題:反米・反帝国主義の継続
・闘争のシンボル化: 在日米軍基地反対運動、特に沖縄の基地問題は、米国の「帝国主義」や日本の「従米姿勢」を批判する格好のシンボルとなりました。この運動は、彼らが長年掲げてきた反米思想の継続を可能にしました。
・主張の矛盾: 進歩派は、在日米軍基地に反対しつつ、日本の再軍備(例:憲法9条改正や自衛隊の軍事力強化)には強く反対します。この「米軍基地はいらないが、米軍の防衛力は必要」という矛盾した立場は、彼らの議論が現実的な安全保障論を欠いていることを示しています。
4.3. マイノリティ運動:国内の「人権問題」への焦点移動
・「正義」の象徴化: 進歩派は、北朝鮮への支持が難しくなったことで、反権力の矛先を国内の保守勢力や日本政府に向け、マイノリティ問題をその闘争の「象徴」として利用するようになりました。
・運動の特徴: LGBTや在日外国人の権利擁護は、「人権」「多様性」を掲げることで保守政権の「伝統主義」や「排他性」を批判する手段となり、国内の「人権問題」に焦点を移すことでイデオロギーの正当性を維持しました。
・マイノリティの「道具化」: 批判者からは、進歩派がマイノリティを社会的弱者の救済として掲げる一方で、それらを単なるイデオロギー闘争の「道具」として利用しているとの指摘がなされています。
5. まとめ
戦後日本の進歩派知識人は、反権力・反米のイデオロギーに基づき、冷戦期には北朝鮮を理想化しました。しかし、拉致問題の公式認定は、そのイデオロギーが現実を無視し、自己矛盾をはらんでいたことを白日の下にさらしました。この失墜を機に、彼らの思想的エネルギーは、韓国問題、在日米軍基地問題、そして国内のマイノリティ運動へとシフトしていきました。これらの新たな運動は、かつての北朝鮮へのシンパシーとは異なる形ではあるものの、依然として「正義」の名のもとに「見たいものだけを見る」という傾向を内包している可能性があります。彼らの思想的変遷は、日本の言論空間におけるイデオロギーと現実認識の複雑な関係を浮き彫りにしています。