イシダイ
- カテゴリ:占い
- 2023/05/28 15:50:22
ニコットおみくじ(2023-05-28の運勢)

こんにちは!気圧の谷の影響で、九州から関東甲信は雲が広がりやすい。
東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨脚が強まる所も。
沖縄は晴れのち曇り。
【イシダイ】 石鯛 Oplegnathus fasciatus
striped beakfish
☆スズキ目スズキ亜目イシダイ科イシダイ属に分類されます魚の一種です。
<概要>
〇名前の由来
イシダイの名前の由来は「魚名考」によりますと、
「石鯛の名の由来は、イシはヒス・ヒシの転呼である」
このように書かれています。
@延喜式(えんぎしき)
「延喜式」には「ヒサウオ」と記録されています。
[延喜式]
「延喜式」という法令集に、
平安京の生活環境を保つことを目的としました清掃の言葉が
数多く記されています。
*平安京・・・現:京都市
「ヒサはヒシ・ヒサと同意の古い漁業用語で、
海中の磯・岩礁のことであるから、
イシダイは磯魚・岩礁魚の意味である」
このようにあります。
このことから・・・
磯の魚でありますから石鯛と書くようになったとあります。
*磯・・・いわば
@江戸時代の食の本の中にも
江戸時代の書かれました食の本「本朝食鑑」には・・・
「色が黒く、肉が硬く、歯が人の歯のようなものを石鯛という」
このように書いてあります。
この本で初めて、イシダイに石鯛の漢字を当てましたようです。
[本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)」
江戸時代の食物書です。
1695年(元禄8年)に12巻12冊本、漢文体で刊行されました。
読み下し本として「東洋文庫(平凡社)さん」に収録されています。
著者は人見必大(ひとみひつだい)さんで医師が職業です。
《人見必大》さん
寛永19年?ー元禄14年6月16日
*寛永19年・・・1642年
*元禄14年6月16日・・・1701年7月21日
江戸前期の本草学者で植物研究家です。
また、幕府の侍医隋祥院も元徳さんの子です。
小野必大さんが本来の氏名で、中国風に野必大とも名乗りました。
先祖が源頼朝公から人見精を与えられたとの伝承によりまして、
人見性を通称としました。
また、千里、丹岳とも号しました。
食生活が豊かになりまして食物と健康の関係に関心が集まりました元禄期に、
本格的な食物本草の所であります「本草食鑑」を刊行しました。
*本草食鑑・・・1697年に刊行
同書は多数の食品を健康への良否を中心に解説しまして、
民間行事や民間伝承の紹介も多く民族的にも重要視されています。
人見必大さんは、延宝元年(1973年)禄300石を継ぎまして、
幕府の医官として波乱なく過ごしました。
〇生息地域・分布
日本各地とハワイに分布します魚で、
水深3~135mの岩礁地帯に生息します魚です。
@分布
北海道以南の浅い海、及び南シナ海沿等に見られまして、
特に西日本沿岸には多く見られる魚です。
〇生態・生育環境
@生育場所・食性
主に岩礁地帯に生育しまして、
頑丈な顎で栄螺(さざえ)等の巻き貝やフジツボ等を嚙み砕きまして
摂食しますのを常としています。
そして、上下それぞれの顎骨は左右が癒合(ゆごう)しまして
嘴(くちばし)のような形をしています。
*癒合・・・生物の組織(皮膚、筋肉、骨等)におきまして、
直近で分かれていました同士が接着しまして、
固着に至りますことを指します。
また、切断によりまして分かれました組織同士が、
接着の働きにより切断面を消しながら元に復すことを指します。
例えば傷が塞がりますことや、
骨折しました骨が正しく繋がりますことが挙げられます。
@棲息地
棲息している場所は沿岸部の暖流の影響があります岩礁域で、
浅い海に多くいます。
成魚は岩の穴や隙間等に棲んでいまして、
海底付近を泳いで生活をしています。
@産卵時期
春から夏で産卵します場所は外海に面しました岸付近で行われています。
その卵の大きさは直径約1mmの浮性卵で、
水温は約20℃で約36時間後には孵化します。
[浮性卵(ふせいらん)pelagic egg]
卵の比重が周りの水の比重よりも小さく、水中を浮遊します卵です。
仔魚の頃は流れ藻に付いて表層を泳ぎまして、
プランクトンや甲殻類を主食にしています。
@岸壁付近に稚魚は棲息している?
体長が10cm前後までは岸壁付近で群れていますのが散見されますが、
この頃あたりからイシダイ特有の歯に形、つまり嘴状に発達します。
そして、浅場での生活を終えますと、岩礁地帯への生活へと移動します。
〇特徴・形態
@幼若漁期
体側に7本の横縞が走りましてシマダイとも呼ばれますが、
成長するに従いまして、この横縞は消えてしまいます。
@老成しました魚体
吻部が黒くなります為、クチグロとも呼ばれています。
全長は最大のものの記録では、80cmの記録が残っています。
@色が銀色に変わる
7本の縞模様にあるといえますが、
実はこの縞模様はイシダイの幼魚期だけのものです。
体長が40cmを超えますと縞模様は消えてしまいます。
そして現れますのが・・・
・銀ワサ
・銀ピシャ
このようにいわれています現象です。
体にありました縞模様に変わりまして、
口の周りを除きまして、体表が銀色に変わります現象をいいます。
@引きの力が凄い!
竿にかかりました場合の力は雄雌に関係無く強烈で、
60cm級を超えるものになりますと、
釣り人の想像を超えます力と引きで我々を楽しませてくれます。
@歯の特徴
あの硬い殻に覆われています栄螺やフジツボを噛み砕きます
硬くて頑丈な歯です。
イシダイの歯は何層にも重なりました小さな歯が石灰質で固まりまして、
あのイシダイ特有の嘴のような形の歯になっています。
古い歯が脱落したり、硬いものを食して欠けましても、
その下から新しい歯が出てきます。
問題 イシダイの幼魚名を教えてください。
1、ルンバソウ
2、サンバソウ
3、サルサソウ
〇幼魚名
この呼び名は能楽の「OO叟(そう)」の踊りに使用されます衣装の
装束の烏帽子(えぼし)の模様が白黒の縞模様ですので、
イシダイがこの烏帽子の模様に似ていることから名付けられました。
ヒント・・・〇能楽のOO叟
日本の伝統芸能です。
式OO(能の翁)です。
翁の舞に続きまして舞う役、或いはその舞事です。
能楽では狂言役者が演じます。
さらにヒント・・・
〇ブラジルの代表的な音楽の一つ
ブラジルでは毎年12月2日を正解の音楽の日と定められていまして、
この日に翌年2月前後に行われます正解の音楽カーニバル曲集が
発表されます他にも、多くのイベントも開催されます。
<2023年東京での正解の音楽のお祭り>
〇ブラジルフェスティバル
日程:7月15日(土)~7月16日(日)
時間:11:00~19:00
場所:代々木公園イベント広場(東京都渋谷区)
〇浅草正解の音楽カーニバル 国内最大規模
日程:9月17日(日)
時間:13:00~18:00
場所:雷門通り「例年は馬車道通り、雷門通り(東京都台東区)」
お分かりの方は数字もしくはイシダイの幼魚名をよろしくお願いします。
















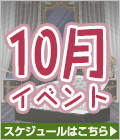










ノエママン、日曜日の夕食の時間帯にコメントとお答えをありがとうございます。
はい、おみくじは「大吉」でした。
どうもありがとうございます。
おお~、分かりましたか、大正解です。
凄いですね、おめでとうございます(祝)
そうですか、解説もありがとうございます。
嬉しいです。
はい、お天気が変わりやすいですので気をつけてまいりましょうね。
今週も大変お世話になりました。
はい、こちらこそ週明け月曜日からよろしくお願いします。
ご多忙のところ、どうもありがとうございました。
日曜、お疲れ様~☆彡(_´Д`)ノ~~オツカレー♪
ニコットおみくじ「大吉」げっちゅ~オメデト~♪OK牧場☆彡(`・ω・´)b
2、サンバソウ(若魚)☆彡(^_^)v
幼魚はシマダイ、サンバソウは若魚らしいッス♪(^_-)-☆
時節柄ご自愛くだしゃんせ~☆彡(*´з`)-♥
無理せず無茶せず体を労わりつつ、週明け月曜からも楽ぴくヨロピク~☆彡◡( ๑❛ᴗ❛ )◡ルン♥