七夕
- カテゴリ:勉強
- 2025/07/07 01:12:48
こんばんは!7日(月)は、
北日本では雲が広がりやすく、所によりにわか雨があるでしょう。
東日本から西日本は広い範囲で晴れますが、
午後は内陸を中心に所々で雨や雷雨がある見込みです。
南西諸島は、東シナ海に進む台風4号の影響で雨が降りやすく、
雷を伴って降る所もありそうです。
強風や高波、土砂災害等に注意してください。
【2025年の七夕の願いごとは?】
A、高温障害によって農作物が被害を受けないようにとお願いをしたいです。
〇高温障害 heat damage
heat stress
☆一般的な表現
■Heat damage
高温によって物や生物に生じる損傷全般(例:電子機器、食材、食品等)
□Heat stress
主に生物(人間、動物、植物)が高温環境で受ける生理的ストレス
<概要>
〇高温障害
気温の高さによって農作物の成育に悪影響が及ぶことを指します。
高温障害によって農作物の品質や収量低下が起こることもあります。
@具体的な障害
・結球性の農作物の小型化 ・肥大不足
・糖度不足 ・短茎
・花の奇形化 ・花色不良
これら等が挙げられます。
高温によって障害が発生するメカニズムは、
まだまだ不明な点が多いのが現状です。
又、品質や収量の低下には、高温によって生じる病虫害の発生や地温上昇、
土壌の水分不足等も関連する為、
様々な要因が絡み合って障害を引き起こしていると推測されています。
★考えられるメカニズム
・高温により、光合成能力が低下する
・高温により、呼吸量が増加する
・代謝異常や消耗が多くなる
@高温障害になりやすい農作物
☆稲
高温障害になりやすい農作物の代表例が稲です。
■高温により起こる影響
・生育の前進で、追肥時期や病害虫防除時期を逃す可能性あり
・出穂時から20日間の平均気温が27℃を超えると、
白末熟粒等が発生しやすくなる
*白末熟粒・・・本来細胞に澱粉(でんぷん)が詰まっていくはずなのに、
澱粉が詰まり切る前に登熟してしまう
・35℃以上の高温が続くことで不稔(ふねん)が発生しやすくなる
*不稔・・・種子が出来なくなる
又、高温状態が続き、
雨が少ない等の条件によって、病害虫被害も増加します。
☆大豆
■高温により起こる影響
・生育が早まる
・茎葉が萎(な)えて、萎(しぼ)んでしまう
・開花期周辺に高温が続くと、開花数の減少や落下が多くなる
☆葉茎菜類(キャベツ、ブロッコリー、ホウレンソウ等)
■育苗期の場合
・発芽不良 ・生育が遅れる
・萎(しお)れる ・葉焼け
これら等が生じます。
□生育中
・生育が遅れる
・結球性の植物の変形
・芯腐れ
・高温による病害の発生「軟腐(なんぷ)病、立枯病、根茎腐敗病等)
・高温による害虫の発生
これら等が挙げられます。
★果菜(かさい)類(キュウリ、トマト、ナス等)
□高温により起こる影響
・害虫の発生が増える(ハダニ類、オオタバコガ等)
・発芽率の低下
・萎れ
・葉焼け
・着果不良
これら等が挙げられます。
★根菜類(ヤマトイモ、サトイモ、ダイコン等)
□高温により起こる影響
・発芽不良
・害虫の発生
・高温で土壌が乾燥することによる収量や品質低下
これら等が挙げられます。
@高温障害予防策
★稲
一番は水の管理です。
生育の様子をよく観察し、状態に応じて水等の管理を行います。
穂ばらみ期以降で高温が続くようなら、放水管理を行います。
*穂ばらみ期・・・幼い穂が急激に成長して、穂と同じくらいになる時期
土が常に湿っている状態を保つ為に潅水して、
足跡に水が残るぐらいまで水が減ったら、再び潅水をします。
又、根を活性化させる為に、出穂前30~50日には追肥を行います。
ケイ酸カリ等を使用して、施肥を行います。
尚、高温により発生しやすい病害虫に関しては、
動向に十分注意をして、普段通り防除に努めます。
☆大豆
高温により茎葉に萎え萎んだ様子が見られた場合は、
日中以外の時間で畦間に潅水をします。
病害虫に対しては動向に注意し、普段通り防除に努めます。
アブラムシ等、発生しやすい病害虫はある程度決まっていますから、
出来る防除法を予め施します。
★野菜
・遮光資材を利用する ・地温上昇抑制資材を利用する
・潅水で土壌水分量を調整する ・肥料等を施し、地力を向上させる
・予め、ハウス等の温度環境を整えておく
【七夕】 たなばた
☆七夕は、中国の七夕に端を欲する日本のお祭りです。
<概要>
〇七夕
織姫様と彦星様が天の川を渡って、1年に1度だけ出会える7月7日の夜です。
短冊に願い事を書いて、笹竹に飾り付けます。
「雨が降ると天の川が渡れない」ともいわれ、
てるてる坊主を吊るした人も多いようです。
かつては旧暦の7月7日でしたので、
現在でいうところの8月上旬から下旬の頃です。
昔は晴天率の高い行事です。
月の動きに基づく旧暦では、7日は必ず半月です。
その月も22~23時頃には西に沈む為、夜半には天の川がよく見える日です。
*地方により、多少時間がずれます
新暦の現在は、凄くざっくり平均すると、晴れる確率は3割位です。
東海地方や山口県等では、
「雨が降った方が縁起が良い」という言い伝えも残っています。
@七夕の歴史・由来
七夕のお話は、中国古代の民間伝承が基になっています。
織姫と彦星は、中国風だと織女(しゅくじょ)と牽牛(けんぎゅう)です。
韓国やベトナムにも七夕があります。
日本には奈良時代に宮中儀式として伝わり、
織姫が機(はた)織りの上手な働き者だったという内容から、
手芸や裁縫の上達を願う風習に繋がりました。
星に願い事をする原型はここから始まっています。
問題 江戸時代になると、七夕は「五節句」の一つとされ、
幕府公式の祝日でした。
〇五節句
季節の変わり目に神様にお供え物をしたり、
邪気払いをしたりして、無病息災を願う年中行事です。
日本に伝わった後、日本古来の腐臭や祭礼と結びつき、
現在の五節句の風習が出来上がりました。
・1月1日:人日(じんじつ) ・3月3日:上巳(じょうし)
・5月5日:端午(たんご) ・7月7日:七夕
・9月9日:重陽(ちょうよう)
五節句は季節の節目にあるおめでたい日と認識されていますが、
基となった中国では「奇数が重なる日=不吉な日」とされ、
邪気払いが行われていました。
七夕についてですが、
次の文章の???に入る言葉をよろしくお願いします。
寺子屋等では紙の短冊に願い事を書き、???の上達を願いました。
1、算術
2、読み書き
3、論語
ヒント・・・〇???
文字の???は1歳~6歳までの個人差が大きく、
環境や興味、関心によって進歩します。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。





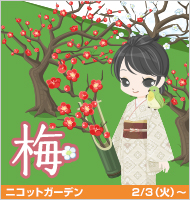




















暑い中、お忙しいところ、コメントをありがとうございます。
そうですね、農作物が被害を受けないようにと私もお願いしたいですね。
問題の答えは、2番の読み書きです。
そうですか、ミスチルさんをお聴きになっていたのですね。
どうですね、高音の部分がありますね。
そうですね、技術が必要ですものね。
答え 2
ミスチルは男性曲なので、
カラオケでは主に聞いていただけです。
どれも結構難しいですよね。特に「innocent world」
上手く歌えた人って私の知り合いではいなかったかも。
おおお~、ミオティカさん、素晴らしいですね。
「読み書き」が正解になります。
あはは、そうなりましたね。
今夜は熱帯夜になりそうでしょうか?
どうか水分補給等をして、お過ごしくださいませ。
〇・・・
読み書き
4つ字・・・だよね?