アユ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/07/09 17:12:08
ニコットおみくじ(2025-07-09の運勢)

こんにちは!九州から東北は晴れる所が多いが、
午後は非常に激しい雨や雷、突風に注意。
北海道は晴れる。
沖縄は曇りのち雨。
全国的に厳しい暑さが続く。
【アユ】 鮎 香魚 年魚 銀口魚 記月魚
Plecoglossus altivelis(Temminck & Schlegel,1846)
Ayu
Sweetfish
☆アユはサケ目(キュウリウオ目)アユ科アユ属の魚です。
<概要>
〇アユ
@生態
★分布
北海道南部から朝鮮半島、ベトナム北部等の東アジア一帯に分布し、
その多くは日本の河川に遡上(そじょう)します。
本来、川と海を回遊する魚で、日本では代表的な川魚です。
秋に河の河口近くで孵化(ふか)したアユの仔魚は、
河口から遠くない範囲の海に出て、
プランクトンや小さなエビ等の動物性のものを食して育ち、
春になると約5~10cmの稚魚となり、
河を遡上し始め、食性も主に岩に付いている藻を食すように変わり、
それに合わせて歯の形状や体色等も変化していき、成魚となります。
□海産、琵琶湖産、人工産
人工産のアユが出て来る以前ですが、海産は体型がスマートで背鰭が短く、
湖産は背鰭が長く、背鰭の黒縞模様がはっきりしています。
例えばですが、天竜川のアユ、安倍川のアユ、
これは狩野川(かのがわ)のアユ等と言い当てる程に、
その川ごとに特徴を持っています。
*天竜川、安倍川、狩野川・・・いずれも静岡県の河川
◆外観で湖産、海産、人工産を見分ける方法
△背鰭大1棘と側線の間に並ぶ鱗の枚数による見分け方
・湖産:25~28枚(仔アユを採捕養成すると枚数が少なくなり、
20以下もある)
・海産:18~23枚
・人工:15~20枚
これだけでは、決め手になりにくいです。
しかし、天然遡上のものは、鱗の枚数が多いことは確かです。
神奈川水産試験場さんでは背鰭第5棘のところで数える方が、
枚数を数えやすいといっています。
その場合、上記の値よりも4~5枚少ない数になります。
▲群馬水産試験場さんが示している見分け方
アユの全体の姿と背鰭の後の部分の鱗の並び方を上側から見る。
・琵琶湖産 :頭は小さく、体高があり、頭は扁平(へんぺい)する。
頭は扁平(へんぺい)している。
背の中央は黒色に近い。
鱗は細かく、配列は規則正しい。
・海産、河川産:頭は中位の大きさで、胴は比較的細い。
背の中央は黒色から褐色。
鱗の大きさは湖産と人工産の中間で、
配列は規則正しい。
・人工産 :頭が大きく、胴が細く、丸い傾向がある。
背の中央は黄色から褐色。
鱗は比較的粗く、大きさは一定しない個体もある。
人工産のアユの特徴は、鱗の大きさを挙げる人がいますが、
初期の段階で塩分濃度の低い海水で飼育する為か、
琵琶湖産のアユと比較しますと、
見た目は肌がざらついている感触があります。
しかし、琵琶湖産同士の交配でも、
人工的に飼育すると、鱗が粗くなることが知られています。
△下顎側線工数(したあごそくせんこうすう)での見分け方
▼天然アユ
海産も湖産も下顎側線孔が4対綺麗に並んでいます。
▽人工産
孔の数が少なく、位置関係も不揃いになっています。
つまり「下顎側線孔数」が4対か否かで見分けられます。
@アユの友釣り
河川のアユは、主に川底の石に付いた藻類を食しています。
この餌場を確保する為に蒸れずに縄張りをつくることも知られていまして、
自分のテリトリーに入り込んできた他のアユを、
体当たりをして追い出そうとします。
この性質を利用して初夏に解禁されるのが、「友釣り」と呼ばれる釣りです。
★アユの餌となる河床付着物の質は、河川流況と密接に関係している
□アユのはみ跡は流心部に多い
(例)
水深 流速
新境川:20cm以上 35cm/s以上
多摩川:35cm以上 65cm/s以上
このようにはみ跡の無い場所と比べると大きいです。
ただし、流速と水深がこの範囲であっても、
水際ではアユのはみ跡は確認出来ませんでした。
■アユのはみ跡は強熱減量(%)と関係が深い
両河川において、アユのはみ跡の有無と強い関連性が認められた項目は、
強熱減量(%)(乾燥重量に占める有機物量の割合)でした。
アユの摂食していたのは強熱減量(%)が高い、
(新境川では約50%以上、多摩川では約40%以上)河床付着物で、
強熱減量(%)の高い河床付着物は流速が高い場合に分布していました。
又、同程度の流速ではありましても、
アユが摂食していない場においては強熱減量(%)が低い傾向がみられ、
摂食している場では強熱減量(%)が高い傾向がみられました。
□アユは藍藻(らんそう)の割合が高い、付着藻を摂食している
付着藻群落の組成についても、流速と関連性が認められ、
流速が高い所(アユが摂食している所)では、
藍藻の割合が高くなる傾向がみられます。
・糸状藍藻のHomoeothrix janthina(ホモエオスリックス)
・Chamaesiphon sp.(カマエシホン)
これらが優先しています。
又、流速の低い所では珪藻(けいそう)の割合が高く、
Achnanthessp.(マガリケイソウ)等が見られました。
@琵琶湖のアユ
琵琶湖に生息するアユは普通のアユのように海には下らずに、
琵琶湖を海の代わりとして利用しています。
春になりますと、琵琶湖に流入している河川へ遡上しまして、
川の苔を食して大きくなるものと、
遡上せずに湖内でミジンコ等、プランクトンを餌として、
大きく成長しないまま、一生を終えるコアユの2系統が存在しています。
これらのアユは普通のアユとは異なりまして、
海水では生きてはいけない体質になっています。
現在、琵琶湖産のアユを他の河川に放流しているケースが多いのですが、
これらが元々のアユと交雑した場合、
その稚魚も又、海では生きられない性質となることは分かっていまして、
本来のアユがそれにより、激減する危惧が唱えられています。
問題 アユの産卵についてですが、次の文章の〇〇に入る言葉を教えてください。
秋になりますとアユは産卵期を迎えて、
体色も〇〇色へと変わり、一匹の雌の産卵に対しまして、
複数の雄が射精することが知られています。
1、赤黒
2、赤褐
3、婚姻
ヒント・・・〇〇〇色
10月下旬から11月中旬に成熟したアユは、
雌雄共に〇〇色が現われ、全身が黒くなり、
流れの緩やかな砂礫底(されきてい)に産卵します。
お分かりの方は数字もしくは文章の中の〇〇に入る言葉をよろしくお願いします。





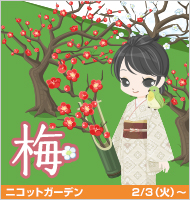




















こうして、コメントをどうもありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
なるほど~、以前に割烹料理店があったのですか。
そうですね、行かない地域に移転だと寂しいですよね。
問題の答えは、3番の婚姻になります。
アユの生育についてですが、我々よりももしかしたら水温の影響が出ているでしょうね。
特に、アユが食す川の苔はデリケートで、
あまりに水温が高いと緑色から茶色になって、いわゆる焼けた状態になります。
そうなると、アユは食さなくなるので、悪循環に入る訳です。
なので、何とか早いうちにこうした温暖化が止まることを心底願っています。
割烹料理店を思い出しました。
行かない地域に移転したので、残念です。
答え 3