センジュガンピ
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/07/11 16:57:58
ニコットおみくじ(2025-07-11の運勢)

こんにちは!湿った空気が入り込み、九州から関東の太平洋側は曇りや雨。
本州の日本海側と北海道は晴れ。
関東は暑さが和らぐ。
沖縄は雨。
【センジュガンピ】 千手岩菲 Lychnis gracillima
Silene gracillima
*英語名については一般的な定着した名所は無く、
「センジュガンピ」は英語圏ではそのまま学名で呼ばれることが多いです
☆ナデシコ科センノウ属の多年草です。
<概要>
〇センジュガンピ
@基本情報
★生息
センジュガンピは山地から亜高山帯の、
林内や林縁の湿り気のある場所でみられる高さ0、4から1mの多年草です。
☆茎
直立して上部で枝分かれし、軟毛が生えます。
★葉
対生(たいせい)する単葉(たんよう)で、
長さが5から14cm、幅が1~3、5cmの披針形(ひしんけい)で、
葉先は尖りまして、無柄で質が薄く、やや軟らかく、
葉の縁は全緑(ぜんりょく)です。
□対生葉序
対生とは茎の1節に対して、2枚の葉が対になります。
最も一般的なのは十字対生であり、隣同士の節の葉が直交します。
特に茎が四角い仲間(例:シソ科)は、十字対生が分かりやすいです。
ヤマノイモのように、植物体の下部は互生(ごせい)して、
上部は対生するような植物もあります。
対生する葉の節間が短く、
輪生(りんせい)のように見える対生葉序は「偽輪生」といいます。
又、ヤエムグラ属やアカネ属のように、
本来の葉と托葉(たくよう)が変化したものが、
輪生するように見えるのも偽輪生といいます。
◆輪生
輪生は植物の茎に葉や枝、花等が輪状に配置される現象で、
植物が効率的に光合成を行う為の基本的な配置パターンの一つです。
輪生を理解することで、
植物の生理や進化メカニズムをよりよく知ることが出来ます。
△輪生の定義と特徴
輪生とは植物の茎において、
1つの節に3枚以上の葉や枝、花が輪状に配置される植物学的現象です。
この配置は、通常は茎の高さに複数の葉や花が、
放射状に広がる形で現れます。
輪生の利点は植物が効率的に光を取り入れる為、
葉の重なりを最小限に抑えることが出来る点にあります。
特に太陽光が真上から差し込むような環境では、
輪生は葉が重なり合うのを防ぎ、
それぞれが十分な光を受けることが出来ます。
又、輪生は植物自身が競争を避ける為の重要な戦略であり、
光合成効率を最大限にする為の工夫といえます。
特に密生した環境で成長する植物には、この配置が有効です。
輪生の特徴を理解することで、
植物の生態や環境適応力についても深く知ることが出来ます。
▲植物の茎における輪生の仕組み
植物の茎における輪生の仕組みは、
葉や花芽が茎の特定の部位で同時に成長することによります。
まず、茎の頂端部分にある成長点からホルモンが分泌されて、
これが葉や花芽の形成を促進します。
次に同じ高さにある複数の成長点から同時に葉や花が形成されまして、
それが輪状に配置されます。
これにより、光を均等に受け取ることが出来まして、
効率的な光合成を行うことが可能です。
この仕組みは、特に光の少ない環境で重要な役割を果たします。
植物が適応する為の真価的な戦略の一つでありまして、
輪生の仕組みを理解することで、
植物の成長や生態系での役割についても、より深く知ることが出来ます。
△他の配置パターンとの比較
輪生は他の配置パターン、特に互生や対生と比較されます。
▼互生(ごせい)
茎の各節に1枚ずつ葉が付きまして、
互い違いに配置されるパターンを指します。
茎に沿って螺旋(らせん)状に葉が並ぶ為、
螺旋葉序と呼ばれることもあります。
互生は輪生に比べて、葉の重なりが少ない為、
光を効率的に利用出来ます。
最終的には各配置パターンにはそれぞれの利点がありまして、
植物はその環境に最適な配置を選択する、
進化的な適応戦略を持っています。
◇托葉
葉の基部に現れる、
葉柄又は花柄を取り囲む小さな葉状の構造のことです。
托葉は葉緑素を持たないことが多く、
その主な役割は若い葉や花を保護することです。
ただし、一部の植物では、
托葉が光合成を行う葉のように発達するものもあります。
托葉の形やサイズは様々で、針状、鱗状、膜状のもの等があります。
又、托葉は葉脈を持たないのが一般的ですが、
一部の植物では葉脈を有するものがあります。
托葉は単独で存在することもありますが、
対生又は輪生で現れることもあります。
★花
2出集散花序に疎(まば)らに付きまして、径約2cmの白色の5弁花です。
□花弁
平らに開きまして、浅く2裂しまして、縁は欠刻状になります。
■雄蕊
10個です。
□萼(がく)
円筒状ですが、果実期には鐘形になります。
■花柄
長さが2から6cmで細長いです。
□果実
卵球形の蒴果(さくか)で、上部が5裂して種子を出します。
@栽培
★増殖
実生(みしょう)、株分け、挿芽(さしめ)によります。
☆生息
日向から半日陰で水捌けが良く、肥沃なやや湿った土壌を好みます。
★水遣り
水切れしないように注意しまして、
鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷりと与えまして、
地植えの場合は夏に晴天が続いて乾燥しない限りは降雨に任せます。
☆施肥
元肥の他、春と秋に緩効性化学肥料を置き肥します。
5月から6月に摘心(てきしん)しますと、脇芽が出て花数が増えます。
★病害虫
特にありません。
@花言葉
中国が原産で、江戸時代に日本に渡来をしたといわれるセンジュガンピは、
観賞用の切花にされる他、薬としての用途もあります。
このセンジュガンピの花言葉は下記の通りです。
・望みを達成する
・明朗(めいろう)
問題 センジュガンピの名前についてです。
次の文章から、センジュガンピが発見された都道府県名を教えてください。
名前はある都道府県日光市中禅寺湖の千住ヶ浜で発見されまして、
中国原産の岩菲(せんのう)に似ることから付けられたとされます。
又、花弁の切れ込みを千手観音の手に例えたとする説もあります。
1、栃木県
2、北海道
3、群馬県
ヒント・・・〇千住ヶ浜
中禅寺湖の西の端にある南北2kmにわたる浜です。
千住ヶ浜は、
日光開山の祖である勝道上人(しょうどうしょうにん)が、
千手観音を見て784年に建てたといわれる、
千手観音堂があった場所でもあります。
この千手堂は1960年代には基礎の石のみの姿になり、
千手堂に来るまで、湖に流れ込む沢が1本ありました。
お分かりの方は数字もしくは、
センジュガンピが発見された都道府県名をよろしくお願いします。





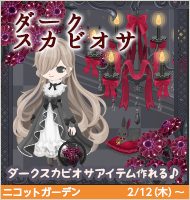




















いえいえ、とんでもありません。
お詳しいご説明をどうもありがとうございます。
そうですか、夏の奥日光はとても涼しい日が多いですよ。
いつの時か、スズラン☆さんが日光を楽しめる日がくることを心より願っています。
センジュガンピのことではなく、
ずっと記載されている植物の中でという意味です。
説明足りなくてすみません。
日光もいつか行ってみたいです♪
そうですね、茎がかなり伸びますね。
おお~、そうですか、対生葉序ですか。
そうですね、お花が開花すると分かりやすいですものね。
そうですか、ブタナがこれに侵略されてかなり数を減らしましたか。
あはは、高山植物ですからどうなのでしょうね?
問題の答えは1番の栃木県が正解になります。
どうもおめでとうございました(祝)
私は若い時に、日光でホテルのアルバイトをしていました。
ホテルは中宮祠という所ではなく、竜頭の滝の近くでした。
約1カ月半のホテルでのルーム等を主に従事していました。
日光の7月の平均気温は分かりますか?現在は20℃です。
かなり涼しかったですよ。
雷雨も多かったのですがw
日光はご存知標高が高い為、高山植物も豊富な土地です。
機会がありましたらですが、スズラン☆さん、奥日光へいかがでしょうか?
個人的には関東地方の中で一番の避暑地ではないかです。
当時はエアコンは必要が無い程、過ごしやすかったです。
茎はかなり伸びるんですね。
実家の低木植物は、対生葉序ですが、未だに花を見れないので、
何なのか分かりません。
ブタナはこれに侵略されてかなり数を減らしました。
いつかここに出てくる花だったらいいなと楽しみにしています(笑)
答え 1