クウシンサイ
- カテゴリ:グルメ
- 2025/09/11 16:18:09
ニコットおみくじ(2025-09-11の運勢)

こんにちは!九州から関東は雨で、太平洋側では大雨になる所も。
北陸、東北は午前に雨。
北海道は晴れるが、所々でにわか雨や雷雨。
沖縄は晴れ。
【クウシンサイ】 空心菜 Ipomoea aquatica Forssk.
Water spinach
Water morning glory
Water convolvulus
Kang Kong
☆クウシンサイは、ヒルガオ科サツマイモ属に属する植物です。
<概要>
〇クウシンサイ
クウシンサイはヒルガオ科サツマイモ属の葉野菜で、
標準和名は「ヨウサイ」とされています。
東南アジアが原産とされ、
日本では沖縄で、ウンチェーバーやウンチェ―と呼ばれ、栽培されてきました。
@クウシンサイの原産地:詳細な地域
★タイ
自生種が多く、古くから食文化に根付いています。
□パット・パック・ブン Stir fried Chinese morning glory
パット・パック・ブンとは「クウシンサイの炒め」のことです。
タイをはじめ、東南アジアの広い範囲で食されている人気の料理です。
プリッキーヌを沢山入れて、辛味を強くしたものを、
パトパック・ブーン・ファイ・デーンと呼ぶこともあります。
この料理は強火で一気に炒めるのがポイントで、
タオチオというタイの豆味噌やオイスターソースの旨味と、
赤唐辛子の辛味がシャキシャキとした食感のクウシンサイに絡むことで、
美味しく食すことが出来ます。
この料理はジャスミンライスとの相性も良いですので、
ライスに乗せて、タレを浸み込ませて食す人も多いです。
☆フィリピン
現地では「Kangkong(カンコン)」と呼ばれ、
川辺や湿地に自生しています。
スープや炒め物に使用される定番野菜です。
★ベトナム
「Rau muong(ラウムオン)」として知られ、
家庭料理や屋台料理に頻繁に登場します。
水辺での栽培が盛んです。
☆マレーシア・インドネシア
両国でも「Kangkung」と呼ばれ、
ナシゴレンやサンバル炒め等に使用されます。
水田や湿地での栽培が一般的です。
★中国南部(広東・福建等)
東南アジアではないものの、華南地域も原産地の一部とされていて、
福建語や広東語で独自の呼称があります。
*独自の呼称・・・例:通菜、抽筋菜
□中国の地方と行政区画:華北・華中・華南・東北・西北・西南
世界史の新課程の用語集では中国の地方名である、
「華北・華中・華南・東北」が新たに用語として掲載されましたが、
このような地方や省の名称と位置を把握しておくことは、
中国史を理解する為に必要です。
◆地方区分について
中国は広大なこともあり、
省等の行政区画よりもさらに大きな空間的枠組みとして、
地方を把握することが有効なのですが、
区分の仕方には様々なものがあります。
しかし、歴史の学習の上では、
華北・華中・華南・東北・西北・西南の6つの地方に分けることが、
特に有益と思われます。
△華北・華中・華南
華北・華中・華南の地域は、
早くから漢民族が支配や抗争を行って「中華」と呼ばれてきた地域で、
その名前の通り、中国の歴史において中心的な地域です。
▼華北
主に黄河の中・下流域を指しまして、
一般的には現在の山東省、山西省、河北省、河南省等、
これらの地域が該当します。
尚、河南省の西の陝西(せんせい)省は、
普通、華北に含めないようですが、
古代史や中世史を学ぶ際には陝西省も、
この地方に含めて考えると良いです。
この地方は黄河文明が生まれた地でありまして、
古代から中国史の中心になりました。
その為、この辺りの地域は中原(ちゅうげん)とも呼ばれまして、
中国の政治の中心になりました。
▽華中
主に長江の中・下流域の地で、
江南(こうなん)と呼ばれる地域ともかなりの部分重なっています。
個々は長江文明の発祥の地でありまして、
黄河文明と並んで中国の文明の主な源流となりました。
古代には華北と比べると政治的に重要な役割を果たさなかったですが、
中世以降に農業や商工業が発展すると中国経済の中心になりまして、
それも背景に、政治的重要性も高めていきました。
▼華南
中国の南東の沿岸部を指しまして、
現在の広東省や福建省等の地を指しています。
広州や泉州のように港湾都市が発達して、
貿易の拠点となったことで有名で、
東アジア、東南アジア、インド、西アジア、
さらにはヨーロッパとの貿易・交流の窓口になりました。
@原産地の特徴
☆気候条件
高温多湿の熱帯・亜熱帯地域が最適です。
水辺や湿地に自然に生育しまして、汽水域でも成長が可能です。
★栽培文化
多くの地域で野生種が存在し、古くから食用として利用されてきました。
特に水耕栽培や浮耕(ふこう)栽培が盛んです。
*浮耕栽培・・・土壌が水に浸かっているような状態で行う耕作方法です。
水田や湿地等で、土が浮いているような環境でも、
栽培できる技術です
☆自生の広がり
熱帯アジアを中心に、熱帯アフリカや東アジアにも広く分布しています。
日本では九州や沖縄等、温暖な地域で栽培されています。
クウシンサイは、どこか一国の固有種というよりも、
東南アジア全域に広く分布する野生種が原型となっていまして、
特定の国に限定されないのが特徴です。
@名前の由来
クウシンサイという名前は、元々中国での呼び名で、
茎の中が空洞になっていることから名付けられました。
@販売
若い葉と茎を食す野菜で、シャキシャキとした食感のある茎と、
少しヌメリを持つ葉が特徴になっています。
中国以外にもタイやフィリピン等の東南アジアの色々な国や、
オーストラリア等では古くから親しまれてきた野菜の一つです。
最近ではスーパー等でクウシンサイのスプラウトも並んでいます。
トウミョウ(豆苗)等と同じように水耕栽培されたものが、
スポンジ床に根を付けたままの状態で、
袋にパック詰めされた状態で販売されています。
問題 クウシンサイの特徴になりますが、
次の文章の???に入る言葉を教えてください。
クウシンサイの葉の形状は細長く、
先が尖った、???の形をしています。
栽培環境等によって、
葉はかなり細長いものからやや幅広タイプ等の違いは出てくるようです。
1、ナイフの刃先
2、矢じり
3、槍(やり)
ヒント・・・〇???
石や骨等で造る、尖った石器のことです。
???とは、武器における刃物の部分で、
木の棒は柄にあり、両方をきちんと固定しないと使用出来ません。
お分かりの方は数字もしくは???に入る言葉をよろしくお願いします。





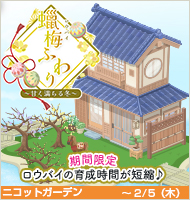





















こんにちは!度々のコメントをありがとうございます。
スズラン☆さん、どうもお疲れ様です。
そうですか、外で食されたことがあるのですね。
はい、近所のイオンさんで販売されていますよ。
地域によってどうかですが、もしかしたらある可能性もです。
はい、次回行かれる場合にいかがでしょうか?
はい、問題の答えですが、2番の矢じりが正解になります。
矢じりは黒曜石という鉱物を使用すると、とても切れやすいです。
ですので、古代の方が料理に使用した包丁の材料にも使用したりされているのですよ。
スーパーにも売っているんですね。ネットスーパーでは見かけないので、
行くことがあれば注意して見たいと思いました。
答え 2