東京明治神宮例祭
- カテゴリ:レジャー/旅行
- 2025/11/03 16:41:38
ニコットおみくじ(2025-11-03の運勢)

こんにちは!冬型の気圧配置となる影響で、全国的に日本海側は雨が降る。
太平洋側は概ね晴れ。
沖縄は晴れのち曇り。
最高気温は平年並みか低い。
【東京明治神宮例祭】 とうきょうめいじじんぐうれいさい
☆明治神宮の例祭は、11月1日から3日まで行われる盛大な祭りです。
例祭期間中は様々な神事や奉納芸能が行われまして、多くの人で賑わいます。
<概要>
〇東京明治神宮例祭
@明治神宮さんでの秋の大祭、2025年の日程や場所
日程は2025年11月1日(土)から、
11月3日(月、文化の日で祝日)までとなっています。
場所は明治神宮さんで、住所は東京都渋谷区神園町1-1です。
明治神宮さんは、大正9年11月1日に創建されました。
明治天皇と昭憲(しょうけん)皇太后が祀られています。
11月1日が「鎮座記念祭」で、
11月3日は明治天皇の誕生日(旧暦の9月22日)を祝う例祭が行われます。
約70万㎡の明治神宮さんには、
全国から集められた多くの木が集められていまして、
その境内で、日本の伝統文化が奉納されます。
元々、この土地は江戸時代初期から、加藤家、井伊家の下屋敷でありましたが、
明治元年、井伊家から政府に献上されました。
面積は約70万㎡で、園内には隔雲亭(かくうんてい)や、
御釣台(おつりだい)、四阿南池(あずまやなんち)、菖蒲田(しょうぶだ)、
清正井(きよまさのい)等があります。
★明治神宮御苑内の名所
□隔雲亭
◆由来
明治天皇が昭憲皇太后の為に建てた御休所(おやすみどころ)です。
◇建築様式
数寄屋(すきや)造りです。
▲数寄屋造り
日本の伝統的な建築様式で、
茶室や小規模な住宅に見られる、質素で洗練されたデザインが特徴です。
▽数寄屋造りの定義
数寄屋造りは茶道文化の影響を受けた建築様式でありまして、
特に茶室の設計において重要な役割を果たしています。
元々は茶事を行う為に、
母屋(おもや)とは別に建てられた小規模な茶室を指しまして、
自然素材を活かした要素でありながら、
美しいデザインが特徴です。
▼特徴
●自然素材を使用
数寄屋造りでは竹や杉、土塁等の自然素材が多く使用されまして、
素材の持つ、風合いを大切にしています。
●シンプルなデザイン
装飾を排除しまして、
シンプルでありながら、繊細な意匠(いしょう)が求められます。
床の間や障子(しょうじ)等、和の要素が取り入れられています。
●風潮を重視
数寄屋造りは和歌や茶道、生け花等の風流を好む人々によって、
磨かれた空間美を反映しています。
●借景(しゃっけい)の利用
周囲の自然や景色を取り入れた設計がされていまして、
四季を感じられるような間取りが考えられています。
▽歴史的背景
数寄屋造りは安土桃山時代に千利休(せんのりきゅう)さんによって、
完成された「侘茶(わびちゃ)」の影響を受けていまして、
無駄を削ぎ落としたシンプルさの中に、
美しさを見だすスタイルが確立されました。
江戸時代以降は茶室だけではなく、
一般の住宅にも数寄屋造りの要素が取り入られるようになりまして、
現代でもその影響が見られます。
▼代表的な建物
数寄屋造りの代表的な建物には、桂離宮(かつらりきゅう)や、
修学院離宮(しゅうがくいんりきゅう)等があります。
これらの建物は、
数寄屋造りの美しさと、その文化的意義を体現しています。
数寄屋造りは、シンプルでありながら、
深い美しさを持つ、日本の伝統的な建築様式がありまして、
現代の建築にも影響を与え続けています。
◇歴史
1900年創建で、戦災で焼失後の1958年に再建されました。
◆特徴
南池を望む位置にありまして、四季折々の庭園美を楽しむことが出来ます。
□御釣台
◆由来
昭憲皇太后が南池で釣りを楽しまれた場所です。
◇位置
南池の畔(ほとり)に設置された釣り台です。
◆特徴
静寂な池の景観とともに、皇室の生活の一端を感じられるスポットです。
□四阿南池
◆読み方の補足
「四阿(あずまや)」は東屋のことで、南池の近くにある東屋を指します。
◇用途
休憩所として利用されまして、池の眺望を楽しむことが出来ます。
◆特徴
自然と調和した木造の小屋で、散策中の憩いの場です。
□菖蒲田
◆見頃
6月中旬がピークです。
◇特徴
約150種の花菖蒲が咲き誇る名所です。
◆由来
江戸時代から続く庭園の一部で、季節の彩りを楽しむことが出来ます。
□清正井
◆由来
加藤清正公が掘ったと伝えられる井戸です。
◇特徴
湧水が絶えず流れまして、パワースポットとしても人気です。
◆注意点
現在は通路が閉鎖されている場合もありますので事前確認が必要です。
これらのスポットは全て明治神宮御苑内にありまして、
歴史と自然が融合した静かな空間です。
特に6月の菖蒲田は圧巻です。
@明治神宮さんの秋の大祭2025年流鏑馬(やぶさめ)や能等、
狂言等のイベント
☆流鏑馬
流鏑馬は疾走する馬上から、
的に目がけて鏑矢(かぶらや)を射る、日本伝統の儀式です。
★舞楽(ぶがく)や能、狂言等
能や狂言、三曲(さんきょく)、舞楽、邦楽邦舞がそれぞれ、
神前舞台で行われます。
◇三曲
三曲は、三種類の楽器「箏(こと・そう)」、三味線、
尺八又は胡弓(こきゅう)にいよる合奏(がっそう)を指します。
▲箏
中国から伝来したもので、
絃(げん)の数や柱の位置で音を変えることが出来ます。
全国弓道大会や古武道大会、合気道演武、
百々手式(ももてしき)等も西参道芝地や宝物殿東芝地等で行われます。
◇百々手式
お払いを受けた射手が矢を射って魔を鎮める儀式です。
境内では菊花展が開かれる他、全国の物産物、銘菓、生花が奉納されます。
問題 流鏑馬が始まった時代についてですが、
次の文章の〇〇に入る時代を教えてください。
始まったのは平安時代といわれまして、
〇〇時代に、幕府の行事で盛んに行われるようになったことから、
武士が武芸の腕を競うものになりました。
1、鎌倉
2、室町
3、江戸
ヒント・・・〇流鏑馬
〇〇時代に武士の軍事訓練として始まり、
後に神事としての意味合いが強化されました。
特に、源頼朝公が武士の鍛錬と武運長久を祈願しまして、
流鏑馬を奨励したことが、その形式の確率に寄与しました。
流鏑馬の名称の由来には諸説あり、流れるように矢を放つことや、
走るの古語「やぶる」からきているという説があります。
お分かりの方は数字もしくは〇〇に入る時代をよろしくお願いします。





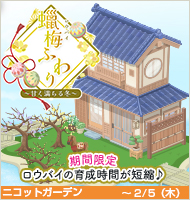























こんばんは!曇りの火曜日をお疲れ様です。
そうでありましたか、明治神宮さんへ行かれたご経験がありましたか。
ああ~、そうですか、やっぱり植物が並びますと嬉しいですよね。
又、神聖な場所ですから、巨木の並木道に圧倒されたのでしょうね。
問題の答えになりますが、1番の鎌倉が正解になります。
スズラン☆さんは、歴史にもお詳しいですね。
スズラン☆さん、どうもおめでとうございました(祝)
以前東京に旅行に行った際、明治神宮に行きました。
古い建物もさることながら、通りに並ぶ巨木の並木道には圧倒されました。
答え 1