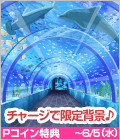「evergreen」
- カテゴリ:自作小説
- 2023/09/23 21:17:32
もうそろそろでしょうか。
朝藤が、開け放たれた窓の向こうを見遣りながら尋ねる。視線の先、裏庭では青々とした梢が薫風に揺れている。今日も今日とて気持ちの良い日和だ。
朝藤は珍しく、他の患者なら忌む窓際のベッドを希望した。窓際で寝食をしようものなら、嫌でも眼下に広がる林が目に付くが、入院した者は大抵この不幸の塊を厭う。しかし彼は達観なのか諦観なのか、目が覚めればいの一番にカーテンを開き果てまで続く木々を視界に収め、五月晴れの朝の光を浴びるのを日課にしていた。
「もうそろそろでしょうね」
傍らに立ち検温をしつつ遊雨子(ゆうこ)は平淡に答える。実際、数値を記録し終えたら早々に患者を裏庭の林へ連れていくつもりだった。彼のベッドの下に、小さな若葉を見つけたから。
おざなりなような返り事に、朝藤は目を細める。男は、変に期待を持たせない遊雨子の物言いが入院当時から好きだった。
遊雨子は、都会の大学病院から山あいのこの国立病院へ移ってきた。腕を見込んで誘われたわけではない。ただ、その顔が美人と呼ばれるたぐいのものだったからだ。
「朝藤さん。ちょっと裏庭へ散歩に行きましょうか」
ボールペンを胸ポケットにしまいながら声をかける。この科白が、末期の水であると朝藤はよく知っている。もうこれ以上を見込めない相手に、そっと死に際を教えるものだと。
朝藤は何も答えていないのに、遊雨子は手を差し伸べた。爪が短く切りそろえられており、病院に勤める者の清潔感と安全への責任感がうかがえる。その手を握った朝藤の爪は同じピンク色の楕円形ではなく、希望の象徴のような新芽だった。
裏庭に到着する頃には、朝藤の膝から下は既に木の根っこに変形していた。おかげで自力での歩行はままならず、遊雨子の肩に腕を回し引き摺られるようにして目的地までいびつな二人三脚で目指す。
とはいえ、階段を降りきってから五月病(さつきやまい)が進行したのは幸いだった。下るさなかならば、女一人で男を運びきるのは困難に近い。遊雨子はここに移ってから日が浅いが新人にありがちな失敗は通っておらず、その見極めが得意なようだった。
一歩遊雨子が歩みを進めるごとに五月病の症状は悪化し、朝藤の胴が幹に変わりつつある。早く林に辿り着かなくては。
遊雨子の新しい勤務先は、奇病「五月病」の終末患者を集め緩和ケアを目的とした病棟だった。
一年の内五月にだけ罹患者が現れることからその名がついたこの病気は、20~30代の若い男の足を根に、胴を幹に、腕を枝に、つまり最終的には一本の木にしてしまう、成す術もなく。二人の目前の林は、かつて男だったものの集合体、成れの果てだった。
木々の間に足を少しだけ踏み入れて、最期に適当な場所を探す。治療法も未だに確立していない中では、患者は若木として扱われ、ベッドではなく土の上で臨終を迎えさせるというのがおおよそ一般的な方針だった。
他の木と適度に距離のある場所を見定め、首を傾けすぐ真横の顔にここでいいかと無言で問う。もとは毛髪だった細い枝が蔦のように男の顔を覆い、無数の葉が遊雨子の耳元でさびしいとざわめく。しかし目をしっかり開いていた朝藤は、かすかに、でも確かにうなずいた。ぎこちない頭部の上下運動を視認した遊雨子は、枝に抱きこまれる寸前だったので素早く体を離し、餞別に義務づけられたキスをおくる。しっかりと朝藤は大地に根を下ろし、もう身動ぎもかなわない。
「好きでした、遊雨子さん」
皮膚が褐色に硬化していく中、まだ柔らかな唇が健気に動く。それが、遺言。分かりきった内容だった。若くして死ぬのならせめて最期に恋を楽しんでもらおうと今際の男と美しい女はここに集められたのだから。微笑みながら献身的に身の世話をしてくれるならと、隔絶された死の淵に憧れる愚か者も一定数存在すると聞く。その噂が耳を掠めたとき、そんな痴れ事をぬかす輩の呑気顔をぜひ見てみたいものだと、毎日怯え顔と向かい合ってきた遊雨子は呆れた。
朝藤だった木に背を向け、建物へと戻る。一度風が吹き、葉擦れの音に呼び声が混じった気がして振り返ったが、林立する男に紛れてどれが彼か遊雨子には見当もつかなかった。