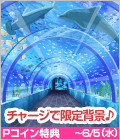「山男とサーファー」12
- カテゴリ:日記
- 2010/09/28 02:52:19
「やってみれば、そんなに難しくはないでしょう」
「常にバランスを保つことに注意しなければならないから、これはかなり習熟を要する技術だな」
「大丈夫ですよ。もう二、三回来て練習すれば、ある程度のタイミングもつかめるし、君だったらできますよ」
「アイスハンマーを引き抜いて、ハーケンを打ち込む時だけが、多少不安だな。ピッケルだけで支えているんだから、突風が来たときはちょっと煽られて、バランスを崩しそうだ・・・」
「それなら一層のこと、アイスハンマーを二本使ったらどうですか? ピッケルとの三本使用だったら、意外と楽かもしれない」
「ハーケンは?」
「オーバーハングなどで使用したらどうですか。場合によっては、アイスピトンやアイススクリューを持っていって、捩じ込んでおいたら、そこでビバークできるかもしてない」
「氷壁に打ち込んでおいて、ハンモックで寝るか」
M君は笑いながら頷いた。
天候の豹変と雪崩の危険性など、たとえ本人が致命的なミスをしなくとも、自然の気紛れさは突如として牙をむく。どのような不測の事態に備えた行動であろうと、それらからは逃れることはできないのだ。まして、今日のような好天になれば、太陽の陽射しによって暖められた氷壁が、いつ崩れ落ちるか分からない。俺はできるだけ、氷壁ではビバークしないつもりでいた。
「戻りますか?」
M君が立ち上がった。
俺は、コッハーのコーヒーの残りを捨てて、立ち上がった。
氷河の上を踏みしめて歩く二人の背中を、汗が伝って流れる。
昨晩までの荒れようが、嘘のようであった。
絹雲は遥か上空を流れ、稜線はしだいに金色に染まりつつあった。
ディアミール氷河のいたる所に、バックリと口を開けているクレバスがあった。俺たちはそれを避けながら、二キロ程下って行った所で、突如背後で、大音響が轟いた。二人とも驚いて振り返ると、氷壁がみごとに崩れ落ちていく。
先程までそこにいた場所が、何百トンもの氷塊に、すっかり埋まっていった。
俺とM君は顔を見合わせた。
「今度は別のところでやりましょう」
M君はニヤリと不敵な笑いを浮かべて、踵を返した。
七
ベースキャンプに戻ると、一番慌てていたのが従弟のS君であった。
T氏とYさんはそうでもなかったが、それでも、突然崩れ落ちた氷壁に、肝を冷やしたようだった。
「危なかったですね。もう三十分とどまっていたら、巻き込まれる所だった」
S君は、うわずった調子で云った。
「運ですよ。この場合、いい方に解釈していいんじゃないんですか」
M君は事も無げに云った。動揺している様子は微塵も見せない。却って俺の方が自然の威力を見せつけられて、多少ナーバスになっていた。
「君たちが出発してから、S君は双眼鏡で、僕は1200ミリの望遠レンズで、君たちの行動やナンガの状態を観察していたんだ」
T氏は、俺のラフマのキスリング(リュックサック)を受け取りながら云った。
「ナンガのあちこちから立ち昇る水蒸気に、Yさんが危険だな、と云ったんです。トランシーバーを持たずに出発したので、すぐにそこを離れるよう、信号弾を発射しようかとも思ったんですが・・・」
S君は、チラリとT氏を見た。
「まあ無事に帰還したんだから、いいじゃないか。夕食にしようよ」
T氏は俺の肩を叩きながら云った。
メタクッカー(固形燃料)の炎に浮かびあがる五人の顔は、思い思いの感慨に耽っているようで、能面のように無表情に黙りこくっていた。