11月自作/「紅葉『松永 椛』」 1
- カテゴリ:自作小説
- 2013/11/10 12:37:05
彼女は人差し指を、俺の鼻に立ててこう言った。
「あれでもさ、根はいいからさ。ちょっと世間知らずなところはあるけど頼んだよ」
「わかってるよ、それをお互い分かってるから付き合ったんだろ?」
その指を左手で振り払いその問いに答えを出すと、共にお互いは苦笑した。
「僕もいい人探さないとなぁ…ねぇ、誰かいい人いたら紹介してよ?」
「あぁ、はいはい。ただ来年でちょっと就活だからそんなすぐには無理だぞ」
冷めかけた珈琲を一気飲みして、俺はそう答えておいた。
「よかったら姉妹盛りなんてどうよ?両手に花って言葉もあるしさ、僕も満更じゃないしね」
そう言って彼女は笑った。いつみても彼女は笑顔がよく似合っていた。
「休みの日に、今度は加奈と一緒に来るから。その時にまたお邪魔するよ」
「今日は顔を見に来てくれただけだしね。また来てくれるのを楽しみにしてるね!にゃはは♪」
「じゃお暇させてもらうわ、そんじゃ」
「ん、それじゃね」
そう言って俺は「彼女の妹」の家から出て、今俺が付き合ってる彼女が待ってるあの家に帰ろうとしていた。
もう時刻は逢魔ヶ刻、空は黄昏て、夕闇に暮れていくそんな時間。
その時に不意に携帯になった。それは突然に恰(あたか)も自然に鳴り響いて驚きなんてしなかった。
いつもそんな感じだったから彼女の思いや、ちょっとして流れいった変化に気付けなかったんだと後になって悔み思った。
木の葉が紅葉に変わるそんな季節、これから一生涯暮らしていく彼女との関係はその一本の電話から終幕を告げられたのであった・・・
*
夏生が俺の隣に引っ越してから、二週間が経とうとしてそんな生活にも慣れてきた今日この頃。
世間は師走の雰囲気に向かいながら、外の温度はどんどんと冬らしくなってきた。
「いや本当に俺は隣に、お前が引っ越してきてくれて良かったと思ってるよ」
ムシャムシャ・・・
「でしょでしょ、巧人は自分で考えて自炊しなさそうだから、この私が来て飯の有り難みに
ついて感謝してくれていいのよ、ふふふ」
ガツガツ・・・
「いや本当に俺の好物知ってるだけで満足だわ、だってこのカツなんて物凄いお前んちの味だし本当に主婦してたんだなぁ」
カチャカチャ・・・
「まぁ言ってそんなに主婦の期間は短かったけど、新しくこうして一人暮らしするようになって新しい感じで楽しいよ」
ズズズ・・・
俺は夏生の部屋で彼女が作ってくれた晩御飯を頂いていた。
ただ二人共付き合っているわけではなく、二人共ご近所付き合いの延長戦としている感じなのでそこまでならないが。
まぁでも彼女が俺のことを好きになってくれているのは薄々感じているつもりである。
だが別に今彼女が欲しいわけでもなく、今はこうして時にたゆたって生活していたいのでお互いそんな感じなんだろうと思う。
その気にでもなれば、夏生と付き合うこともあるんだろうけど、
前の彼女「加奈」に申し訳が立たないし、そんな軽い気持ちで付き合うのはどうかと思うので今はこれでいいんだと自分に言い聞かせている。
フラフラしてるように見られてるかもしれないが、これでも俺は俺なりに思っている志(こころざし)は持っている。勘違いはされたくないし・・・
それにしても夏生の飯は旨い。幼馴染み効果なのかはわからないが、「食欲の秋」とはよく言ったものだなぁ…秋は本当に食欲が進む、進む。
この今日の晩ご飯の味噌汁に豚カツは、本当に「家庭の味」がして本当に心地のいいものである。
よく昔は家がお隣でご近所付き合いの良かった夏生の家に、御飯を食べに行くことも少なくなかったので稗田家の食卓の味は覚えているつもりだ。
そう考えるとお袋、お母さんの存在を暖かく染み染み感じる処があるなぁ…と自分ながら感傷的になりつつも、とっとと飯を平らげるのであった。
そしてパンと軽く手を鳴らし
「御馳走様でした」
と
「はい、お粗末さまでした。じゃ食器片付けてくるから帰った帰った!」
夏生は腰まで伸びた長髪をポニーテールにしてヘアゴムで結うと、シッシと追い払う仕草をした。
「わーったよ、じゃまた呼んでくれよ。ありがとな」
「ん!じゃーね、ふふっ」
そして夏生の部屋を出て、自分の部屋に戻ろうと廊下に出ると俺の部屋の部屋のドアの隣にしゃがみこんでる人がいた。
小学生くらいの背丈に合わない大人のコートに身を包んで軽く波うっている黒色の髪。
そのウェーブがかかった髪の毛は鎖骨にかかる長さで、その隣にちょこんと置かれたトランク。
刹那、嫌な予感が走った。何故かって?俺は昔にも同じ経験をしている、そして俺はこの体育座りをする人、いや女性の面影を知っていたから・・・
俺は額に掌を当てて、深く深く肺から空気を吐き切る様に溜め息をついて、その女性も何故今更に俺に会いに来るのだか・・・
いや別にそこまで迷惑じゃないのが「タチが悪い」と言うのか、何と言うのか、ふむ
取り敢えず此処で立ち往生してても仕方ないので、俺は開けたくもない口を開けてその女性に話しかけたのだった。
「おい、椛!手前俺の家の目の前で何してやがる!」
椛(もみじ)、俺がそう呼んだ女性はゆっくりと頭を上げると虚ろな目で俺を見定めると、俺に向かって飛び掛ってきた。
「やっと見つけた!!!」
「ぐふっ……なんか最近・・・昔の女に追いかけられる災難ついてない俺?はっ…ははっ…はははっ…」
止まらぬ苦笑い、最近愛想笑いが板につきすぎてしまってる。「気がする」ではなくて、いやこれ結構本気で。
「お兄ちゃん、久々!元気にしてた?ちゃんと食生活ちゃんとしてる?就活できてるの?新しい彼女さんとかは?」
「あー、だぁ!もううっせ!」
すると隣から扉が開く音が聴こえた。
「これはヤバい」そう瞬時に思った俺は、即座に行動を起こした。
「ねぇ巧人、今なんかうるさい音がしなかった?ってあれ?」
そこには誰もおらず、ただ一陣の風だけが通り抜けていた。
「あれ?今でもなんか落としたような?気の所為かな、いいや食器洗ってこよ」
隣の部屋のドアが閉まる音を聴くと、俺は安堵の溜め息をついて自分の部屋に即座に吹っ飛ばした椛とトランクを睨みつけた。
「にゃはは、相変わらず凄い馬鹿力だね・・・」
「ふっざけんなって、マジで…アイツにだけは見つかったらまた面倒な事になるんだからマジで頼むよ・・・」
「…ごめん」
しょげて椛はぽつり謝罪の言葉を漏らした。
この椛という女性は、俺が先程話していた亡くなった彼女「加奈」の妹「松永椛」である。
未だに…と言うかコイツは昔から一人称が「僕」だったりするので、
昔は良く口調で男と間違えられたりもしてたが、今の容姿は物凄く女の子なので今はもうそんな事もないか。
「ってか、お前も何しに来たんだよ。」
「『お前も』ってこの前も誰か来たみたいな言い方だね、前に誰か来たの?」
「隣に住んでるのが夏生なんだよ、態々(わざわざ)俺の家を調べて隣に引っ越してきやがったんだよ。」
「あー、夏生さんなら平然とやりそうだね。納得」
人差し指を唇に当てて、上を見上げる仕草をして苦笑する椛。
「まぁ僕もお姉ちゃんが亡くなった歳にもなったので、この機会にお兄ちゃんにあってこようかなと。先に言っておくけど、連絡したのに全然出なかったのお兄ちゃんだよ?」
「は、マジで言ってる?」
だとしても全然、頭に入ってないぞ。
「はぁ…、本当にあれから変わってないね」
そう言うと椛はゆっくり俺の元に来て、自然と俺の唇に唇を交えるのだった…





















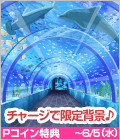





http://www.nicotto.jp/blog/detail?user_id=442098&aid=53157657