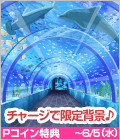ながら寝返りを打
- カテゴリ:日記
- 2013/09/25 12:47:08
坤备钉堡皮浃盲评搐毪趣盲筏悚盲皮欷蓼筏俊?
「わかった。ありがとう」
浜松で長い時間顔を合わせているのはよくないということで、牛太郎は善兵衛を岡崎に帰した。
「ししし」
「何笑ってんだ、ジジイ」
「楽しくなってきましたよ」
牛太郎は新三や於松に計画の全貌を明らかにしていない。それでも、於松は悪事に鼻がきくのだから、もしも敵であったらと思うと、怖くなってくる。
「あ、そっか」
だったら、その怖さを利用すればいい。
「おい、じいさん。甲府に忍び込んでこい。下人でも草履取りでもいいから、武田の誰かに雇ってもらえ」
「ええっ?」
と、飛び上がったのは新三。
「そんなの無理ですよ。於松殿にそんな無茶をさせるなんて。だいたい、尾張訛りですぐにわかってしまいますよ」
「喋らなければいいだろ」
「そんな無茶苦茶な」
「ししし。いいんですかい」
「お前、そういうの好きだろ、どうせ」
「よくご存知で」
牛太郎は新三に言って、荷駄の中から竹細工の籠を取り出させ、その中にしまい込んでいた梓の小袖を手に取る。新三が眉をしかめる中、一度、香りを確かめると、その袖から二枚の大判を取り出した。
ぽいと於松の前に放り投げる。
「駄賃だ。好きに使え」
「へへっ。さすが旦那」
於松はみすぼらしい歯を見せて笑いながら、大判を懐にしまい込む。
「で、あっしはどうすればいいんでしょ」
「変な真似はしなくていい。その汚い鼻をきかせて、武田の怪しいところを探ってこい」
於松はほくほく顔で宿を出ていった。
「大丈夫なのですか、於松殿を甲府などに行かせてしまって」
夜、布団を並べていると、新三がぽつりとそう言った。
「死に損ないだ。ちょっとやそっとじゃ死なないだろ」
「そういうことではなくて、逆に於松殿が寝返って、殿のことを武田にべらべらと話してしまったら、それこそ、忍びを警戒している意味がなくなってしまうのではないのですか」
ふん、と、牛太郎は笑いながら寝返りを打つ。
「大丈夫だ。あのジジイは絶対に寝返らない」
「どうしてですか。何か根拠でもあるのですか」
「勘だ」
悪党の。
翌日、牛太郎は昼前には浜松の城下を出て、新三と共に三方ヶ原方面へと街道を歩んだ。
暦の上では春に入って間もないが、浜松一帯は季節が充ちたような暖かさで、夏を待ちわびる田畑が広がっている。
「一年前が嘘みたいだ」
無論、あのときは遠州の空っ風が手足をかじかませる冬だった。その寒さも忘れるほどの激戦だった。血と汗が飛び交い、牛太郎自身も山県三郎兵衛尉に耳を裂かれ、汗を滲ませながら命からがら栗綱を駆け抜けさせた。
真っ赤に染まった夕空が瞼の裏に焼きついている。
多くの男が散っていった。牛太郎の知人だけでも、中根平左衛門、青木新五郎、夏目二郎左衛門、平手甚左衛門。
あれからもう一年が経っている。それでも、まだ、一年しか経っていない。三方ヶ原の激戦から今まで、実に長い年月が降り注がれたようで、しかし、あっと言う間にまたここにやって来てしまったような心持ちでもある。
広大な三方ヶ原台地までやって来る。目の前には春の乳白色の空が広がり、そこに白や黄の野花が色を添えていた。
「殿」
気付けば、新三が振り返ってきている。
「ああ、すまない」
牛太郎は再び歩み始める。
しばらく行くと、なるほど、道端にぽつんと一軒、茶屋とは思えぬあばら家があって、ただし、濡れ縁を外に並べているところを見ると、やはり茶屋らしい。薄暗い中を覗き込んでみると、老婆がたった一人、亡霊のように座っていて、一瞬、牛太郎も新三も後ずさりしてしまった。
「い、一服、出してくれるかな」
「あいよお」