アイス・ティアーズ
- カテゴリ:自作小説
- 2017/03/11 13:05:16
目が覚めると、何故かいつも泣いている。
それがいつから始まったのか。
もう、細かいことは覚えていない。
ただ、朝目覚める時、本当は清々しい気持ちで目覚めたいが、頬を伝うのは冷たい涙だった。
どうして泣いているのか、夢で哀しいことでもあったのか。
目が覚めると、いつもどんな夢を見ていたのか覚えていないから、泣いている理由もわからないまま年数は過ぎて行っていた。
「いつまで寝ているの?」
こぼれ落ちる幾筋もの涙を指先でなぞるように触れていると、ノックもなしに扉が開き、同居人が顔を出した。
少しニキビの浮かぶ頬を膨らませて、呆れたように立っている同居人に、僕は涙を流していることを伝えていなかった。
何故か、伝えられなかった。
きっとそれは、彼女に泣いているという情けない事実を伝えたくない、一種の照れ隠しなのだろう。
「ごめんごめん。起きるよ」
「早くしてね?もう朝ご飯出来ちゃっているから」
「すぐに支度して行くよ」
にっこり、これこそ朝に相応しい笑顔を浮かべ、彼女は部屋を出て行く。
ほんの少し濡れた指先を布団で拭い、今日も僕は立ち上がる。
いつから泣くようになってしまったのか。
無表情で真顔が多く、涙は勿論、笑顔も見せる機会がなかった。
僕がこうなってしまったのは、幼い頃の経験が土台として僕を創りあげているからだろう。
幼くして両親を事故で亡くし、親戚の家を転々としてきた。
親戚はどこの家もあたたかく僕を迎え入れてくれて、大学まで行かせてくれた。
でも、どこか居候の身である事実がどこの家でも存在して、僕は亡き家族を想い涙しているのを決して見せようとしなかった。
涙を見せぬ者に、笑顔は浮かばぬ。
誰かが言っていた言葉の通り、僕は涙も笑顔も見せぬ人へと成長していた。
浪人することなく大学へ進み、大手とは言えないけど安定した会社に就職して。
淡々と、浅い人間関係を壊さぬよう、必死に日常を守っていた。
その途中で出会ったのが、同居している彼女。
無表情だと言われ続けてきた僕と正反対で、明るく優しい、笑顔の素敵な彼女。
映画館で僕の飲み物を間違えて飲んでしまったことがきっかけで、知り合った。
僕の彼女だと言うと、周りの人間はいつだって驚いていた。
僕と正反対で、笑顔の素敵な彼女。
僕と一緒になって不安だって多くあるだろうに、彼女はいつだって僕の傍にいてくれた。
そこで物語のように笑顔が僕に戻れば良いのだけど、現実はそう簡単にいかなくて。
結んでも、生活は変わらなかった。
変わらなかった、はずなのに。
何故か、朝目覚めると泣くようになっていた。
数十年間抑え続け、見ることは死ぬまで、死んでからもないだろうと思っていたのに。
僕の前に突然現れた冷たい水は、必ず頬を伝っていた。
「そうだ。
わたし、今日早く行かなくちゃ」
「そうか」
「帰るの遅くなると思う。
先に何か買って食べて、寝ちゃっていて良いから」
「わかった」
素早く身支度を整える彼女を横目で追い、黙々と彼女が焼き上げた食パンを食べる。
「じゃあ行ってくるね」
「……」
鞄を持ってリビングを出ようとする彼女を見た時。
ズキン、と何故か頭が酷く痛んだ。
「行ってきま」
「待って!」
立ち上がり、思わず腕を引いた。
「…どうしたの。大声なんて出して珍しい」
「……あの、」
引き止めたのは良いものの、何を言いたいのかわからず口ごもる。
「…?」
「……何でもない」
「そう?…じゃあ、行ってきます」
パタンと扉が閉まる音がした瞬間。
僕は、膝からその場に崩れ落ちていた。
泣きたくない。
涙なんて、見せたくない。
それはまるで呪文のように。
僕をゆっくり蝕んでいた。
「……」
目が覚めると、何故かいつも泣いている。
いつから涙をこぼし始めたのか。
細かいことは、何ひとつ覚えていない。
ただ、朝目が覚めると、必ず涙を流していた。
「いつまで寝ているの?」
呆れたように頬を膨らませ、ノックもしないで扉を開けた彼女。
見せないよう急いで目元を乱暴に拭い、「起きるよ」と短く答える。
彼女は「朝ご飯出来ちゃっているから」と部屋を出て行った。
身支度を終えリビングへ入ると、彼女は慌ただしく準備をしていた。
「わたし、今日は早く行かなくちゃ」
「そうか」
「帰るの遅くなると思うから、先何か買って食べちゃって寝ていて良いから。
お金は置いてあるから」
「わかった」
彼女が毎朝焼き上げてくれる、食パン。
齧っている間にも、彼女は準備を進めていた。
「行ってきま」
「待って!」
サクリと食パンを齧る音と、ズキンと痛んだ頭の音。
気付いたら立ち上がり、彼女の腕を引いていた。
「…どうしたの。大声出すなんて珍しい」
「……」
何で、引き止めた?
どうして、大声を出した?
「……?」
「…何でもない。行って…らっしゃい」
「行ってきます」
パタンと扉が閉まる音。
それが何故か、酷く苦しい。
「……行かないで」
行っちゃ、駄目だ。
その言葉をかき消すように、
僕は膝から崩れ落ちた。
☆
「ごめんなさい、間違えちゃいました…」
困ったように謝って来た、彼女。
「関節キス、ですね?なんちゃって」
柔らかく、照れたように笑う彼女が可愛くて。
「はあ…?」と緊張感が全くない声が出て、映画の内容は全て吹き飛んだ。
「お詫びに、近くにあるレストランに行きませんか?
奢りますよ!」
無邪気に手を引く彼女が、酷く愛おしくて。
「詐欺なんかじゃないですよ。
むしろわたし、嘘が大嫌いな人間なんです」
真っ直ぐな瞳に、彼女の本心を見つけた。
「わたし、実はさっきの映画、彼氏と来る予定だったんです。
でも、彼氏ってば酷くて…他に好きな人が出来たって、今朝電話でドタキャンされちゃったんですよ?
家に引きこもってヤケ酒でもしようと思ったのですけど、映画のチケット勿体ないから仕方なく来たんです。
それがまさか、新しい出会いがあるなんて…人生捨てたものじゃないですよね」
アルコールで顔を赤く染め、彼女は笑いながら言っていた。
「…初恋だったんです。
本当に、大好きだったんです…彼のこと。
最近わたしを見てくれないなって…寂しい気持ちを、必死に殺して。
本当に…本当に、大好き、だったんです…」
笑っている彼女の頬に、透明な涙が伝った。
「ごめんなさい。
初対面の人に愚痴なんてしちゃって…。
でもわたし、ひとりっ子で両親を早くに亡くしていて、天涯孤独なんです。
人間関係を作るのも苦手で…友達も実はゼロで。
愚痴なんて聞いてくれる相手…あなたしかいないんです」
初対面の僕に、心を簡単に開いて。
馬鹿だと思う半面、僕しかいないと真っ直ぐ伝えて来た彼女を、見捨てることなんて出来なかった。
「僕で、良ければ」
「え?」
「いつでも話、聞きますよ。…まぁ、聞くだけしか出来ませんけど」
「それだけで十分です!
だって、聞いてくれる人がいるってだけで、安心出来ますから!
ありがとうございます!」
真っ直ぐで素直な性格ゆえ、人間関係を作るのが苦手な彼女。
無表情で怖いと言われ、人間関係を作るのが同じく苦手な僕。
お互いがお互いを必要とし、打ち解けるのに時間なんてなかった。
「……好きです。僕と、付き合ってください」
「…え?」
「え?」
「わたしたち、もう付き合っていたんじゃないんですか?
やだ…わたし、勘違いしちゃっていました」
「……」
「改めて、よろしくお願いします!」
「…よろしく、お願いします」
敬語もいつしかお互いの言葉から抜けて、一緒に出掛けて、手を繋いで、簡単にだけど唇を重ね合って。
お揃いの銀色に輝く輪を身に着けて、ひとつ屋根の下愛を囁き合って。
生きていて良かった。
幸せだ。
彼女のことが…本気で、世界で一番、大好きだった。
続きます






















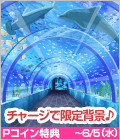


こういう出会い方はないかもしれませんけど
映画館で隣の人に飲み物を飲まれた経験はある人が多いみたいです
私はないですけどね笑
おぉ気付きましたか!
次…うーん、いつになりますかねぇ…?
久しぶりですね~
前のは放置されてしまっています笑
誤字ですね!
関節にキスはしないと思います…多分笑
出会いが面白いですね
同じようなフレーズが繰り返されますが?
夢と現実?
次、読みたいですね^^
関節キス → 間接キス
かな?ってところ、一か所あるぞ!!ま、ほんとに、関節にキスしたのかもしれんけど!??ww