経済成長の目安を変えるべし
- カテゴリ:ニュース
- 2010/06/07 23:18:16
今日の各社の報道によると、政府の専門家会議が日本の景気は昨年3月に底打ちしている、という判断をしたそうである。
言いかえれば、昨年3月で不況は終わっていて今は回復期にあるという事になる。
しかし回復期に入ってもう1年以上経っている、と言われてそれを実感できる庶民がどれぐらいいるだろうか?
我輩もしがないサラリーマンだからそんな実感はない。むしろうちの会社や業界では今が最悪期のような感じさえする。
景気がいいとか悪いとか言う場合、いろんな経済データが使われるわけだが、基本的にはある国の経済力を測る指標はGDPである。
これは日本なら日本で一年間に新しく生産、販売された物やサービスの値段の合計。これが何%増えたから、今年の成長率は何%という話になる。
数年前から知られるようになったが、ブータンという小国がGDPならぬGNH(Gross National Happiness)という概念を提唱している。「国民総幸福量」と訳される。
簡単に言えば、物質的、金銭的な豊かさではなく、精神的な豊かさを大事にしようという話だ。
GNH自体はどうやって計算しているのかはっきりしない部分も多く、良く言えばスローガン、悪く言えば言葉の遊びでしかない。
だから日本がGNHを導入しろと言うつもりはない。
ただ、GDPというのは「マクロ経済指標」と言って、国全体の経済力を測るには都合のいい数字だが、それが一人一人の庶民の豊かさとイコールとは限らない。
一握りの富裕層が国の富の大半を独占しているような国は世界にはごまんとある。戦前の日本もそうだった。
そして近年、日本でもGDPの大きさイコール国民の豊かさとは言いきれなくなってきた。
「一人当たり国民所得」という経済指標がある。
「先進国クラブ」とも言われるOECDという国際機関の加盟国30カ国中、日本は1992年には4位だった。が、2007年には19位に後退した。
ちなみにこの時期、日本のGDPはまだアメリカに次いで世界第2位だった。
そろそろGDPでも中国に抜かれそうだが、庶民の実感により近い一人当たり国民所得では、とっくの昔から日本の凋落は始まっていたのである。
ちなみに2000年代のOECD中1位の常連はルクセンブルグ。、アメリカでも中国でもイギリスでもドイツでもない。
こう言っては失礼だろうが、日本と比べても吹けば飛びそうな小国だ。だが豊かな国が多い西欧でも特に豊かな国として知られている。
政権が民主党に移っても、国の経済政策と言うと相変わらずGDPが増えた減った、という事で一喜一憂している点は変わっていないようだ。
だが日本は中国のようなこれから発展する国ではなく、既に十分経済成長を遂げた、言わば壮年期の国家である。
豊かさを測る指標が、少なくとも政府の経済政策の目安が、いつまでも成長期と同じGDPであっていいのだろうか?
GNHに変えろとは言わないが、例えば一人当たり国民所得などの庶民の実感に近い指標をいかに上げるか、という姿勢に転換すべき時期に来ているのではないだろうか?
国敗れて山河あり、と言う。国栄えて万骨枯る、という未来だけはご免こうむりたいものだ。





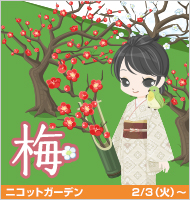



















それはさておき、小泉政権下の長期に渡る好景気においても、ついに一般国民はその恩恵を実感することなく終わってしまいました。
お金が入っているのに国民に循環してこない仕組みを改善しない限り国民の生活の向上はないわけで、引いては国の発展はないでしょうね。
こんな感じのCMが流れる時代だった
http://www.youtube.com/watch?v=EyzjjCSNvF8&feature=related
まるで、今の中国のようだ
「東京ラブストーリー」だの
「マハラジャ」だの
テレビから流れてくる
それらの、当時、大人が夢中になってる事に
子供ながらに、品性の下劣さを感じていたし
「どうせ、こんな風潮、いつか終わるだろ・・・」
と思っていた
GDP(生産)する為に生まれてきたワケじゃないんだし
これからは、家族や地域の身の回りを大事にしたほうが
イイですね
(GDPで豊かになれると身を粉にしてきた、
あの世代の人達は、余暇産業に目を向ければ良いんじゃないかな?)
もう、紙幣信奉(労働信奉)では
人類は幸せになれないと思う