上司に読ませたい本
- カテゴリ:30代以上
- 2010/12/04 13:34:37
今年通年のベストセラー書籍の第一位が「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」だったそうだ。
いくつもの意味で今の時代を反映している現象だと思う。
まず「真面目くさった物は通用しない」という事を証明したという点が新しい。
「真面目である」と「真面目くさっている」は全然違う。
頭の古い「真面目くさった」人間はこの本には手も出さないだろう。
我輩は発売後間もなく買って読んでみたのだが、見た目はまるでラノベである。サイズは単行本だが。
表紙だけ見たらコミックか?と思った人も多いだろう。
ただ中身は非常に真面目である。だが、真面目くさってはいない。そこがうけたのだろう。
「ドラッカー」というのは世界的に有名な経済学者であり、いわゆる「経営学」という概念の発明者とも言われるピーター・ドラッカーの事である。
ナチス時代にヨーロッパからアメリカに亡命したユダヤ人で、その業績の大半はアメリカ移住後の物である。
アメリカでは経営者や管理職のバイブルのように扱われている。
ドラッカー以前のアメリカ企業には「マネジメント」という概念そのものがないに等しく、管理職というのは、まるで奴隷監督官みたいな物だったそうだ。
そこへ心理学に基づく「人間心理を利用して部下にやる気を出させる方法」という概念を持ち込んだのがドラッカーである。
これが「経営学」という新しい学問の誕生だった。
ただし、ドラッカーの経営理論は複数の著作と大学教授時代の論文の内容の総称であり、日本語訳が出ているものだけでも全て読破するのは相当しんどい。
また内容もけっこう難解で、そう気軽に読める本ではない。
だから日本では大企業の管理職であっても「ドラッカーって何?」と言う人が珍しくない。
「もし高校野球の・・・」は、このドラッカーの経営学の理論を弱小高校野球部の女子マネージャーの取るべき行動として描写した、一種の娯楽小説の形になっている。
だから特に学識のない人でも気楽に読めて、かつドラッカーの理論のサワリの部分を楽しみながら理解できるようになっている。
ただ、企業のマネジメントにすぐに役立つかは疑問だが。それでも経営学という概念そのものを全然知らずに管理職やるよりはましだろう。
これがベストセラーNo.1になったもう一つの大きな意味は、それだけ進むべき方向性を見失っている企業人が多いという事だろう。
ドラッカーの理論は経営者や管理職のための物だが、別に平社員が読んで悪い事はない。むしろ本当に優れた上司とダメ上司を見分ける力がつくから、平社員にこそ必読の書かもしれない。
少なくとも、ドラッカーの名前も知らなかった人が「もし高校野球の・・・」を読んだ事がきっかけで経営学理論に興味を持ったら、それは大いに結構な事だ。
ドラッカーの理論の中身は多岐に渡るが、我輩が個人的に心酔しているのは「常に自分にとっての反対者を身近に置け」という部分である。
これは若いころのドラッカーがナチスの脅威を実際に体験した事から生まれた教訓だと思う。
ナチスの本質は独裁者とイエスマンの集団だという事だ。現代で言えば北朝鮮のような社会だ。
そして企業というのも、うっかりすると同じ状態に陥りやすい。
顧客やユーザーを二の次にして、社内でのゴマすり合戦、派閥抗争に目の色を変え、そしてその組織そのものが自滅へひた走る。
過去に「えっ!あそこが?」と言いたくなるような老舗、名門、大企業が倒産したりした場合、その内部は必ずこういう状態に陥っていたらしい。
上記の教訓は「自分にすり寄って来る部下にこそ気をつけろ」と言い換える事もできる。
そんなの常識だろ?と思うかもしれないが、これを理解していない管理職は信じられないほど多い。我輩の職場もそうである。
その結果、経営が傾き、人材が次々に流出し、にっちもさっちも行かなくなって、やっと「何とかしなきゃ!」と気づくのだが、その時はたいてい既に手遅れである。
かくいう我輩もつい先日、31社目の応募にチャレンジして見事玉砕したところである。
現在32社目に履歴書を送って連絡待ち。
が、近年の大学生の就職活動では一人で百社も二百社も受けたなんて話が珍しくないようだ。
ここは「まだ、たったの32」と思うべきなのだろう。
なんとか早く転職先を見つけたいのだが、こうなったらドラッカーでも読みながら気長にやるとしよう。





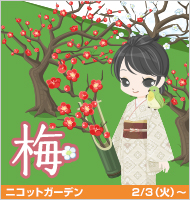




















装丁が、想定外なところも、、