新聞の進むべき道
- カテゴリ:ニュース
- 2011/01/04 21:31:04
クラレという会社の調査で、新聞離れの深刻さが改めて裏付けられた。
調査は昨年9月の時点だが、20代のなんと74.4%が新聞を全く取っていない、という結果が出たそうだ。
雑誌など他の紙媒体への支出も軒並み減っていて、ケータイとインターネットに使うお金だけは増えているそうだ。
我輩は「新聞離れ」という言葉が好きではない。
特に新聞社の人間がこれを口にするのを聞くと、心底ムカつく。
新聞業界の人間なら「読者離れ」と言うべきではないのか?
また新聞社に限らず、マスメディアの世界の人間が「メディア・リテラシー」という言葉を平然と使うのもムカつく。
「ネット・リテラシー」なら分かる。
インターネット上の情報というのは玉石混交で、中には相当いかがわしい情報や、知ったかぶりのネット右翼、ネット左翼のいいかげんな情報もある。
「玉」と「石」を自分で見分けるのは素人にはなかなか難しい。
しかしネットを使う以上、身につけなければならない能力である。
「リテラシー」というのは、この信用できる情報と、うさんくさい情報を見分ける能力の事だ。
だが「メディア・リテラシー」という言葉は存在そのものが自己矛盾である。
インターネットの出現以前にも、世間には様々な情報源があった。
それもまた玉石混交であり、中にはひどいデマもあった。
その情報の中から「石」を取り除き、「玉」を選りすぐって一般大衆に届ける。
それが本来のマスメディアの仕事であるはずだ。
だから新聞のような権威あるメディアの提供する情報は「信用できる物」であり、かつ「学歴のない一般庶民にも容易に理解できる形」でなければならないはずだ。
「メディア・リテラシー」という言葉は言い換えれば、こういう話にならないか?
「新聞などのマスメディアに載っている情報は玉石混交だから、デマに踊らされないように注意しましょう」
あるいは「新聞の文章は一般人には理解できないから、理解できるようになるために、無知無教養な庶民はもっと勉強しなさい」
これはマスメディアの存在価値そのものを否定する話である。
だから「メディア・リテラシー」という言葉を、当のマスメディアで働いている人間が肯定的な意味で口にするのは、自分自身の存在価値を否定する行為なのでは?
現在の全国紙はもちろん、地域紙などの大手、準大手の新聞社のルーツは多くの場合、明治後期から大正時代に盛り上がった「自由民権運動」にある。
当時の一般庶民は義務教育を終えるだけで精一杯で、今で言えば高校進学は金持ちの特権だった。
だから議会政治の重要性だの、普通選挙がなぜ必要なのか、といった話をそのままでは理解できない人が圧倒的多数だった。
特に政治家や役人の発表する情報は、ことさら難しい漢字や単語や言い回しを使っていたため、一般庶民には理解不能な事が多かった。
その理解不能な情報の内容を「無知無学な一般庶民でも正確に理解できるような文章に直して」届ける。
当時の新聞はそういうメディアであったからこそ、大衆の支持を受けられ今日の姿にまで発展できた。
その新聞の内容を理解するために特別な勉強が必要、などと言うのは本末転倒もはなはだしい。
マスメディア、特に新聞というのはあくまで「無知無学な庶民」のためにこそ存在する物でなくてはならない。
新聞社が「新聞離れ」を食い止める方法は一つしかない。
もう一度、自由民権運動時代の、自らの原点に帰ることである。





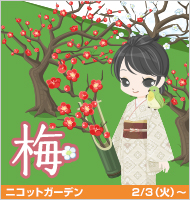



















学校ではよく、新聞は読みなさい、とは言われますが
正直、朝の眠たい目をこすって、1分さえ貴重な時間に、
頑張って新聞に目を通そうとしたって何一つ頭に入らないです。
特に政治欄はそうですね。
法案やそれに関係のある言葉など、知識として知っていなければ到底読めないです。
特に朝寝ぼけてる時間は尚更……。
高校生にも100%読める程度、とまでは言いませんが
60%くらい理解できる表現でもバチは当たらないんじゃないの……?と思います……。
ちょっと話は違うんだけど、4年ほど前、某大手新聞の番組紹介記事を読んでいて、
明らかに文章が間違っているのに、驚きました。
番組欄って、年齢関係なく見るところでしょう?なのに、文章がおかしいなんて。
校正入ってるはずなのに、どうして?って、思いました。
その後、度々、なんていうんだろ。。。俳句で言うと、文字足らず?みたいな、
違和感を覚えるような、記事がおおくて。(中身のことじゃなく、明らかな間違いね)
新聞社には、優秀な人が採用されるハズなのに。
なんだか、世の中、いろんなものの水準が低くなっちゃってる気がします。
こんなことで、いいのかなぁ。
それが、時代の流れで、馴染んで行かなくちゃダメなのかな?って、疑問です。
昔、新聞配達やっていたのでいろいろ考えます。
あの仕事は時間制約が多く、収入の割に大変なので
夕刊廃止やコンビニ限定販売にしてほしいと思うけど、
それだと新聞配達の仕事がなくなるし複雑です。
愚民ども、新聞も読まんのか!って。
もしドラが売れたように、易しい解説にはニーズがあるように思えますね。
っていっても、私は新聞を読みませんが。。
ただ、新聞もテレビもメディアは自分の都合のいいことを都合のいいようにしか報じませんから、公になっているからそれが正しいことだとも言い切れないと思いませんか?
活字になると、なんだか正しいことのように思えてしまいますが、本当に何が起こっているのか、何が問題なのかは、自分の経験等から感じ、考えるしかないのかなぁと思います。
メディアも組織である以上、情報を加工して見せてるのは、仕方ないかもしれません。
それは、本当は、とても恐ろしいことなんでしょうけれどね。
最近、どのメディアも報道の仕方がちょっと変だなと思うのは、私だけなのでしょうか…。
ちょっと論旨がずれてしまいましたけれど、私はメディアには「世論を作ろう」としないで、ただ現実をあるがままに報道してほしいなと思っています。
それをもとにどう考え、感じ、行動するかは私たちにゆだねてほしいです。
そのくらいは、人として成長していたいと思いませんか?^^
新聞を始めとするマスメディアは広告主のための存在になってしまっていると思います。
だから複数の自動車会社が同様のトラブルを起していても特定業者だけが叩かれるなんてことが平然と行われたりもする。
(報道を捏造するのは問題視されても、どれを取捨選択するかは問題とされないから。)
経済団体が従業員の給与を下げたいと思えば比較的高給であった銀行員やそれなりに安定している公務員などを集中的に追及する。
(マスメディア自身にこそ、正規職員の厚遇や非正規職員・下請け等との待遇格差など現在の問題が集積しているだろうに。)
自由民権運動時代、記者は決して優遇などされていなかったけど自分達で道を切り開いてきたはず。
社屋と記者クラブの机の上でしか仕事をしていないような人が大勢を占めて作成している読み物が「読者離れ」を起すのは当然といえます。