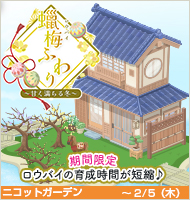きらきら、伊豆旅行、帰ってきました その1
- カテゴリ:タウン
- 2019/10/27 08:35:10
仮想タウンでキラキラを集めました。
2019/10/27

| 集めた場所 | 個数 |
|---|---|
| おしゃべり広場 | 3 |
| 自然広場 | 4 |
きらきら、おしゃべり、自然、三択ルフィ。
十月下旬の日曜と月曜で、伊豆に一泊の旅行に出かけてきた。伊豆も箱根と同様に東京に住んでいる自分には行きやすい場所なので、もう何度も出かけている。
なのに、なぜ…。きっかけは些細なことだ。ウインドーショッピング的に宿を検索したり、パンフレットを見ることをたまにしている。掲載された美味しそうな料理や温泉の情報などを見ているだけで楽しい。
そんななか、西伊豆の土肥で、よさげな宿を見つけたので、出かけることにしたのだった。空想を楽しんでいたのが現実に、といった感じ。
伊豆にはもう何度も…と思ったが、東伊豆が多く、海のない中伊豆、運転免許がないわたしにとって、今まですこし遠かった西伊豆は少なかった。車以外だと、西伊豆を走る電車がないので、バスかフェリーで行くことになる。だから、泊まるところにした土肥も初めての場所。もっとも今回は車だけれど。
何度も行っている伊豆半島。でも初めて…。そんなことをおそらくどこかで意識していた。あるいは旅に出かけるまえに脳内で宿を探すように旅をすることを。旅行に行く前に、旅行ガイドやネットなどで出かけるところをあらかじめ探した。今は観光協会などで出しているパンフレットがPDFで取り出せるから便利だ。そんな作業を楽しんでいる自分がいる。
今回の旅行はほぼ、あらかじめ決めたルートにしたがってのものだった。最初は三島と沼津の真ん中あたりにある、清水町にある柿田川湧水群。ここは以前から気になっていたところ。富士山の雨や雪解け水が地下に染み込み、約八五〇〇年前の噴火の跡である三島溶岩流の先端から湧き出た水とのこと。
水が好きなので湧水群ということばに惹かれ、ずっと行きたいと思っていた場所だった。写真などで見ると、とにかく水が澄んでいる。
実際に行くと湧水群なのだから、周りはもっと緑が深いのだろうと思ったが、国道沿いで、近くまできていても、なんというか、水のある雰囲気はまったくない。車が多く、道の両脇にはどこにでもあるスーパーやチェーン店が立ち並ぶ。だが「柿田川湧水公園」の案内の看板が。入ると芝生広場として開けたところで、噴水や人工のせせらぎがあり、本当に公園といった感じで、湧水群らしくないのが少しおかしかった。広場は柿田川の岸に沿った高台にあるようだ。広場から下った緑深い場所が湧水群で、下りきったところが柿田川。最初に第一展望台のほうへ向かう。緑が多く、渓谷といった感じだなあと思う。
第一展望台は柿田川の最上流になるそうだ。国道下から突然に湧き出て、川が始まる。川というか大きな泉といった感じ。湧き出る水で砂が動くのがわかる。展望台にはガイドの方がいて、地下水だから、その前の週に通った台風の影響もほとんどないといっていた。ガイドの方が、あの黒いのが鮎ですよと教えてくれた。最初、どれを指しているのかわからない。「いつもこんなにいないんですが、台風で逃げてきたんでしょうね」とのこと。まだわからない。指しているものと、指されているものが一致しないと、存在しない。ことばの不思議さに気づかされつつ、一致させるべく、川を見る。澄んだ水たちの放つ様々な色合い、青にうすい緑、暗い影の光、などに惹かれながら。言葉では、そこにいるのに、実物と一致しない、存在しない鮎たち。
だが、ほかの観光客の方から、救いのような言葉が発せられた。「あの水草みたいな黒い塊が鮎なの?」
たしかに川のなかに水草のような黒い塊があった。水のなかでゆらゆらしている。それが鮎が一致した瞬間だった。目の前に鮎がいる、それも無数の、うごめくものたちとして。うれしかった。鮎と水。
第二展望台に向かう。緑のなかをぬけるのだが、そこかしこに染み出る水があり、心地よい。
第二展望台から見る湧水は、昔紡績工場が井戸として利用していたとのことで、井戸の丸い輪のなかから湧き出る水を上から眺める感じだ。砂と陽の光、深さの関係なのだろうか、輪のなかの水がサファイアのような真の青、美しい水色で、あまりに青が濃すぎて、違和感すら感じてしまうが、これが現実の色なのだ、ということに、心地よい水を受け取る。幻想と現実の境目にある青といえばいいのか。ただただその色に魅せられた。
そのあとは木製の八つ橋をとおって散策する。柿田川中流の流れを見たり、あちこちに染み出る湧水や、その小さな流れを感じる。うちの近所にも湧水はある。それを思い出し、比べる。特に小さな流れが地面をぬらしながら這う姿。見た目は似ているけれど、この場所は圧倒的だ。豊富な水が、力をくれるような、清冽さが、あたりに満ちている。いにしえの人々が水に見えない力を感じたことなどを想起する。そういえば、この公園内には水の神様である貴船神社の分社があった。守っている狛犬がどこか愛らしい。
次は村の駅へ。ちょうど昼ご飯を食べる頃だったので。飲食店や物販店が集まっている。野菜、とくにキノコ類が東京では見ることのないものがあり、興味深い。このあたりは椎茸の産地でもあるそうだ。沼津で獲れた鰺のフライ、そしてキノコの味噌汁などで昼食を。値段は比較的安価だったが、とてもおいしかった。
そのあとで伊豆の真ん中をさらに南下する感じで上白岩遺跡と隣接した伊豆市資料館へ。遺跡には縄文時代中期から晩期の環状列石遺構があるという。資料館はそこからの出土品などが展示されている。資料館に駐車場があることもあり、最初にそちらに行く。入口には黒曜石が石碑のように埋まっている。磨いていないので、くすんでいる。だがつい、触ってしまう。触っているうち、磨いたあとの鮮やかなきらめきも思い浮かべることができた。このあたりも黒曜石の産地なのだとか。
資料館のなかでは、発掘された黒曜石のやじり、埋がめとして使われた縄文土器などが展示されていた。埋がめは、おそらく埋葬で使われたのではとのこと。そして石斧、顔面把手、石棒。顔面把手は、部分出土のようだったが、土偶みたいだった。口を開けた姿がなにかを伝えるようで、印象深い。
資料館を出て、道を挟んだところにある上白岩遺跡へ。遺跡は広いくぼみのなかにあったが、遺構や住居址のある場所には入れず、くぼみにそってコの字になった三片を下方から歩いてそれを眺める感じだ。コの字の上方に竪穴式住居を復元したものがある。だいぶ手入れされていないようで、入口に大きな蜘蛛が陣取った蜘蛛の巣。茅葺きの屋根も孔があいていたり、蔓草が巻き付いている。
二つの場所は旅行ガイドなどには載っていない。伊豆市のサイトに載っていただけだ。観光としてはあまり力が入っていないようだった。そのことをすこし寂しく思いながら、次の場所へ。
(続きます)
いつも読んでくださって、ありがとうございます。