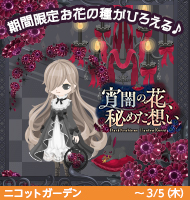利益の出しかた
- カテゴリ:20代
- 2013/04/02 09:44:32
利益の出し方について
まず利益の定義ですが、
(交易で得られる差益)についてです。
この稿ではもっと大きな意味での利益について
述べたいと思いますが、
利益の出し方は簡単です。
1.必要なところに必要なものを持っていく。
2.需要があるものを調達する。
の2つです。
1については、
必要なものを調達しても、届ける先が無ければ意味がない。
必要なものを届ける先があっても、肝心の必要なものがなければ意味がない、
という点からきています。
2については、
市場(ここでは原理)の必要としているものを
どこかから調達・売却することによって、
市場の要求を満たす、というものです。
1について簡単に例えると、(いらないかもしれませんが)
交易の基本です。
需要も、運搬もなければ意味がないという点です。
2については、
好景気で工業品が要求される、
などの例です。
全体の流れが要求を生み出すといった例です。
1についていえば、
供給だけの交易も
要求だけの市場要求も、
意味がないという意味です。
つまり両者のマッチがないと
要求と供給は成り立たないという意味です。
(そういう意味ではフィリップ曲線は簡単)
ちなみに、「供給そのものが需要を生み出す」という
迷言(?)もあります。
これは過剰供給があたらしいニーズを生み出す、という
例えです。
食料品が過剰に供給されると
贅沢な食事をしたがる人が増えるのといっしょです。
2についていえば、
供給品を用意することによって、
新しい市場を開く、といったことが挙げられます。
鉄材を持ち込めば、
工業製品ができる、といった具合にです。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
贅沢品についていうと、
金利調整のためのものだと分かります。
要は、余剰資金を消化するための
金融商品、という意味です。
(贅沢品を買うことは、本来の意味では価値がほとんどないこと)
まあ、好きなものを買うことについては何の異論もありませんが。
*-*-*-*-*-*-*
結論
必要は需要を生む、という点です。
ようは、用意されたものは食え というわけです。
市場に溢れているものについて、要る・いらない理論を唱えても
意味がない、ということです。
その意味では、自動車などの工業品を過剰に供給する
最近の日本企業については目に余るものがあります。
いるものは要るし、要らないものはいらないのです。