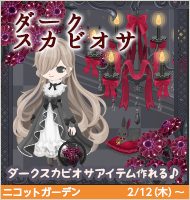等価交換と医学
- カテゴリ:20代
- 2013/04/07 19:35:54
等価交換と医学
等価交換は、なにかを奪ったらなにか代償を払わなくてはならない
あるいは、なにかを与えたらなにかを得られるといった類の用語である。
(→鋼錬、錬金術(本))
医学は、ものの奪い合いに敏感な分野である。
肉体に手術を加える、お金を取って治療を施す など
医学の発展の歴史からしても、錬金術との関連は見逃せない事実である。
ちなみに、錬金術は古代の科学といってもいいようなものであり
その技術自体は現代の科学にも応用されている(→詳しくは錬金術〈本〉)
哲学的な観点の解釈を加えたのが錬金術であり、
医学はそれの影響も受けて発展してきた。
もちろん、ガレノス学派などの経緯を経てなのであるが
錬金術は体の気のバランスで人体を科学することを
試みている。
ちなみにガレノスはもろ体のバランス説を否定した立場であったの
だが、
現代では量子力学などの発展もあり、見直す見方が出てきてもいいように
思う。
極論すると錬金術と医学は同時に発展してきた、とも
言えるのだが、
ようは概念の立場で見ると医学と錬金術は同系列とも
言えるのである。(これについては賛成・反対両論あるかもしれない)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
さて、話は医学のはなしに戻るのだが
等価交換を数式で解釈するとすると、
=・≠は無意味ということが導き出される。
簡単にいえば、感覚に数式が先立つことはないというのが
正確だろうが、これについては反対意見もあるものと思われる。
医学は等価交換を求めるものである。
反対に、等価交換に求められるものであるともいえる。
理由は、唯一取引してはならないのが人間の体だからである。
(→ヴェニスの商人などが好例)
つまり、等価交換を理解し受け入れたものでなければ
医学は務まらないというのが、本稿の立場である。
ある種原理主義ともとれるが、それはさておき
人体を扱うということは、それだけ代償を求められるものである。
その際には、分析哲学に代表される哲学の類が有用となる。
全体を理解・認識できるものでなければ医療は務まらないというのが
その主要な意見である。
つまりは、自分を犠牲にできるものでなければ医療はできない
というのが主旨である。
その代価に報酬が見合っているかどうか、という議論は別にして。
その代償を受け入れられるものでなければ医学はできないというのが
立場である。
現代の医学からすれば厳しい見方かもしれないが、
法則などに代表される原理が重要視されるのは今も昔も変わらないものと
思われる。
勿論医学についていまさらどうのこうの言おうというつもりはないが、
ようは原理からすると学問は分かりやすい、というところである。
その原理が揺らぐのも、現代学問の常なのだが。