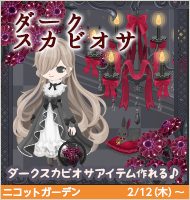ゲーム理論に死す
- カテゴリ:20代
- 2013/10/04 10:43:40
ゲーム理論は、ものごとの関係性に着目し、
特にその利益について詳しく解析した分野である。
というのはおいといてですね。
ゲーム理論にも限界があります。
人間は、一人の人間の枠を超えることはできません。
すなわち、一人の人間が一人の人間よりデカくなることはないのです。
身長が2倍、3倍にもなったら怖いですよね。
人間が超えられるのは、人間同士の相関性、
すなわち物事の相関性だけなのです。
それを結ぶのが、空です。
すべての概念を包摂し得る、大きな概念です。
空を分かりやすく表現すると、
あってもいいし、なくてもいい。
あるとも言えるし、ないとも言える。
というのが空です。
もちろん、その先もあるのですが、
世の中にあるものはすべて空で表せます。
例えば、絶対的に存在するものはありません。
モノは、時が来れば必ず壊れます。
もちろん、それが何年先になるかは分かりませんが。
もちろん、存在していても
使われる意味がなければ存在しないも同然です。
誰が動かない機械を持っていますか?
誰がほとんど働かない2,30年前のストーブを
持っているというんですか?
そういうのを空と言います。
あってもいいし、なくてもいい。
すべてのものの頂点は、ここにあります。
つまり、絶対的なものなどない
ということなのです。
ゲーム理論の限界は、
人が一人の範囲を超えることはない、
ということです。
例えば、一人の人間が大量の情報を持っていても
その一人の人間が一日に消費できる情報量には
限りがあります。
つまり、ネットを使わない限り情報量の消費には限度があるのです。
もちろん、ネットを使っていても多少処理量が増えるだけで
情報量の消費には限りがあります。
健全に使う範囲においては、ネットを使ってもリアルだけでも一緒でしょう。
もちろん、これは1つの着目点に絞らなかった場合であり、
例えば、出会いに着目を置くならば
一人の人間が受け持てる人の数には限度がありますから、
ネットを使ったほうが効率がよくなります。
ただ、すべての情報量を勘案に入れた場合、
会うだけがすべてではないので
トータルで見れば何をやっても一緒
どういう手段をとっても一緒
というのがゲーム理論の空になります。
ゲーム理論は、何をどうやればどれだけ利益が得られる
という筋の理論ですので、
どういう手段をとっても一緒なら
ゲーム理論はそもそも成立しません。
コンピューター同士でゲームをやらせるのなら
別です。
ただ、その場合もコンピューターの情報量という
ボトルネック(限界)が存在するので
実際のプレイヤーがやる、リアルには勝てないのです。
つまり、オンラインで拡張性を持たせないと
そもそもゲームの意味がない。
今までのオフラインゲームは単なる練習だったのです。
ただ、オンラインゲームでも限界があります。
アップデートにはお金がかかります。
なので回数にも限りがあります。
情報量はものすごい速さで増えます。
じゃぁ、それにどうやって対応するかというと
プレイのスタイルを制限することによって
アップデートを誘導するのです。
つまり、合理的な不満がでないように
運営するのです。
それができるのは、
リアル設定の、リアル世界のゲームだけです。
ちょっとでもリアルからのバイアスのずれ(数値のずれ)があると
不満が出てきます。
それは蓄積して、ゲームの限界になります。
最初からゲームに限界があると分かっている場合は、誰もやりません。
可能性があると思うからこそ、やるのです。
なので物量的限界の視点では何も利益がなく、
物事の相関性にのみ可能性があるのです。
交易の基本と一緒です。
最初は、いらないものを交換していました。
それが交易の始まりです。
ということは、作ったら売れる
は全くのウソです。
作り過ぎると、儲かりませんからね。
かといって、何かのために作っても
儲かりません。
もし売れなかったら、ただの損ですからね。
じゃぁ、何かというと
余ったものを売るから交易が成り立つのです。
最初はいらないものの売り買いでした。
そこで成り立っているのは、
相関性です。
なにが必要で、なにが不要かという相関性です。
つまり、これからの時代を作る可能性があるのは、
相関性です。
膨張ではありません。
経済成長をしたからといって、何もないのです。
真の成長を求めるのなら、
横の広がりなのです。
物量的膨張には、限度があります。
なら、物事の関係性は、どうか。
物事はすべて関係しながら存在しています。
関係のない物事など存在しません。
なら、物事の未来は相関性が築くのか。
それは、フタを開けてみないと分かりません。
ただ、その関係性を拓く可能性があるのが、
ゲーム理論のエッセンスです。
ゲーム理論自体は、
全体の限界量(インフレベース)が限界になっていますので、
(例えばゲームにないことは存在しえないのです)
役に立ちませんが
そのエッセンス自体(法則性)は役に立ちます。
例えば、どちらかが有利だからそっちにつけば
どれだけ利益が得られて……だとか
どちらかが見切りをつけたほうがいいから
これはもう放棄したほうがどれだけ利益が得られて……など
そういったエッセンス自体は役に立つ可能性があるのです。
なので、この理論を統合すると
ゲーム理論単体ではそこまで大したことはできないけど、
複数の要素を合わせることで
様々な可能性を生み出す可能性がある
ということなのです。
この複数の要素を組み合わせることは、
相関性を指しています。
つまり、相関性がなければ組み合わせはできません。
人間の子供ですら、遺伝子同士の相関性はあります。
話が逸れましたね。
まとめると、
相関性が未来を生み出す可能性がある
ということなのですが、
よく考えれば当然のことなのです。
関係のないことなどありません。
じゃぁ、その関係性が未来を作ります。
じゃぁ、その未来はどうやって作ったらいいか。
答えは、その相関性の中にあるのです。
人間の科学は、物事の仕組み・相関性を理解することで
成り立ってきました。
ゲーム理論も、その途上で出来たものです。
もっとも、もっと前から存在したかもしれないし、
あるいは、ごく最近できたものなのかもしれないのです。
相関性のみが、物事を発展させる可能性を秘めています。
物量的膨張は、限界があり
最初から愚かなだけです。
なので、平均的成長にのみ意味があります。
例えば、世の中すべての人が幸せになるとか、
世界中から差別・戦争がなくなる、とか
そういったことにのみ
成長の余地があるのです。
相関性が、物事を発展させ得ます。
膨張は、意味がないのです。
人間が動物的愚かさから抜け出せるか否かは、
今このときにかかっています。