喫茶について考えてみる。
- カテゴリ:20代
- 2013/12/10 20:14:14
喫茶という文化
喫茶というものは、いつから始まったんでしょうか。
紀元前でしょうかね~
三国志の時代には、すでにお茶があります。
もっと前からあったと思われますが、
その当時でも高級品なので
やはり王族だけのもの、ということだったんでしょうか~。
世界で喫茶が嗜まれるようになったのは、
おそらく交易のためでしょう~
コーヒーの場合は、
アラビアやアフリカから運ばれたのが最初だと思います。
カカオは、大航海時代の船ですね。
カリブから運ばれています。
紅茶も、ヨーロッパで飲まれるようになったのは
大航海時代前後の話だと思いますが。
喫茶というと、定義的には
お湯か水で何かを煎じるか、
あるいは蒸す・淹れるなどすると
飲めるものすべて(を飲む)ということでしょうか~
正確には、淹れたものを飲む
でしょうかね~
ただ、お酒は喫茶とは呼べませんから、
やはり湯で何かを煎れた場合に
喫茶と呼ぶんでしょう。
蒸す・焼くといった
風習と同様に、
文化の起源としては
かなり古くからある調理法だと言えるでしょうね。
その中でも、飲み物を淹れて楽しむといった
風習はかなり高尚な楽しみだったと言えます。
喫茶はかなり古くからある、
高度な趣味だったと言えます。
歴史の中の喫茶
スパイスを嗜む、
お茶を淹れるといった風習は、
総じて喫茶であると言えます。
なぜなら、それは食事という本来
必要なこと以外に
楽しみという意味で人間が生活に
取り入れたことだからです。
その意味で、スパイスやお茶は
楽しみだったと言えます。
また、その中から体に効果があるものが
薬として珍重されたのでしょう。
それこそ、薬は現在でもプラシーボと言われる
わけですから、
効果があると思って使えば
なんでも薬になるわけです。
そのためには、風習上高度で効果があると
認められる必要があるわけです。
喫茶は、楽しみのために開発されました。
ということは、王族にはもっぱらの楽しみとして
取り入れられたことでしょう。
儀式に喫茶に近い風習が見られるのも、
それです。
原始文化では生け贄ないし
献上品を捧げる習慣がありました。
そのうちお酒や嗜好品が捧げられるようになります。
まぁ、もっとも農耕文明では穀物かもしれません。
食べ物とは違うかたちで
生活に取り入れられたものは、
すべて喫茶であるともいえます。
タバコの場合は喫煙だとも言えます。
ただ、食べるもので食事の目的以外に
飲まれるものはすべて喫茶です。
つまり、食事に次いで(食事は絶対必要です)
喫茶が出てきたのは当然だとも言えます。
あとは、最近でてきた酸素カプセルなどの
リラックス手段でしょうか。
そのうち、冬眠や睡眠するための装置ができるかも
しれませんね~
(冬眠に人間らしさがあるかどうかは
置いておきます(笑))
つまり、喫茶は風習としては
人類にとって当然の行為だったと言えます。
歴史上必要だったから
喫茶は発明されたのでしょう。
もっとも、喫茶は食事となんら変わりありませんから
発明と呼ぶのはちょっと滑稽かもしれませんが。
なぜ喫茶は発明されたか
おそらく、これを掘り起こすのは
いささか愚行かもしれません。
なんせ、食事についで発明されたものを
掘り起こすのですから、
これこそ無謀だと言うほかありません。
ただ、それは火の発見のあとだったと
思われます。
温泉に薬草を入れて飲んだものを、
喫茶と呼びますか?
もしそうなら、話は違いますが
少なくとも人類が建物を作って
暮らした後ですから、
狩猟や採集だけで暮らしていた時代の
だいぶ後ということになります。
もっとも、火の発明された後でなら
どの時期でもあり得るわけです。
火も建築もない状態で
喫茶の風習なんて考えられますか?
もし温泉に薬草を浸けて飲んだら
それは喫茶ですか?
という話になってしまいます。
おそらく、喫茶(いわゆる趣味としての)が
発明されたのは火と建築が発明された後でしょう。
建物も火もないのに、
食料を楽しんで飲むというのはあまり考えられません。
もっとも、水に何か浸して飲むなら
それも喫茶だというなら、
むしろそれは薬でしょう。
最低限、摂取の対象は
嗜好品である必要があって、
医療行為が目的だったら
それは喫茶ではありません。
ただの薬です。
もっとも、喫茶の始まりは
薬の摂取が起点だったかもしれませんが。
明確な喫茶の始まりは、
おそらく茶の摂取でしょう。
薬草をお湯か水に浸して飲むのが
喫茶だったら、
それはさっき言ったように医療行為です。
嗜好が目的で、
植物やその種などを煎じて飲むのなら
喫茶と言えます。
(もっとも、種は薬草に入るかもしれませんが)
そういう意味では、
ただの趣味だったとも言えます。
もっとも、スポーツ・戦争以外に
楽しいことですから、
それが広まるのは難しいことではなかったと
思います。
ただ、喫茶を「何かを煎じて飲む」から喫茶だ
としてしまうと、
薬も入ってしまいます。
ただ、薬はプラシーボだとすると
やはりそういう括りでしか喫茶は表せないのではないでしょうか。
薬なのか嗜好なのか
という話になると
それは個人の解釈で、
ということになってしまいます。
嗜好品でも体に効く場合がありますし
薬でも人によっては嗜好になります。
(麻薬はダメですよ!)
そういう意味では
楽しんで飲んでいたら
なんでも喫茶、ということです。
食べる以外の風習として、
喫茶があるということです。
すべてはフェアネスのもとで
喫茶は人類にとって重要な文化です。
ただ、それはすべての人間が平等である上で
成り立つのが大前提です。
コーヒー、カカオなどの原料は
未だに発展途上国頼りです。
アフリカやカリブの人々を苦しませる形で
喫茶は存在するべきではありません。
フェアトレードというものもありますが
あれも正しいか定かではありません。
喫茶を楽しむのなら、
どこで栽培されたとか
どうやって作られたかを考えるべきです。
それを楽しんで喫茶だとも言えます。
不公平が生じる状態で
喫茶は成り立ちません。
原料については
平等が成り立った上で
喫茶が行われるべきだ、と思います。





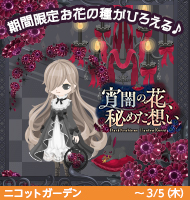























神様と半分この神様は、
自然の叡智という意味です。
つまり、自然の営みと人間の叡智で
半分こ、という意味ですねb
神様は人間が作ったものなので
自然の叡智を神様と表現しただけねb
もっとも、自然の叡智が人間を作ったとも、
人間が自然の叡智を定義した、とも
どちらとも言えますが
おおいなる自然の何か、
を表現するなら、
やはり自然の叡智なのですよね~
文語的には、神様とも~b
いいなぁ~お茶飲むときにそんなこと考えながら飲むとほっこりしそうですね~
理由はさまざまだけど、お茶もココアもコーヒーも
とっても穏やかで豊かな気持ちにさせてくれますね~(´∀`*)♪
It's all in one かぁ…♪(´∀`*)
茶葉は使われるためにあるので~´∀`)
でまたその茶葉も自然から半分いただいたものなのです~
完全に自生している茶ノ木なら
分かりませんが~
人間が半分栽培している以上
自然と文化の賜物半分半分ですね~´∀`)
そういう意味で、宮廷の庭で茶ノ木を栽培していた人は
そういう気持ちだったのではないでしょうか~
皇帝=神 だから神から授かったものでもあるし、
人知で授かったものでもあるから~´ω`)
良かれと思ってやったことが報われないって良くありますよね~pq
って関係ないか…(´∀`*)、
白湯も薬になるくらいだから…わたしは苦手だけどpq
お水ならいくらでも飲めるのに白湯だと飲みにくいデス
きっとそんなわたしのために神さまは茶葉を用意してくれたのかも~(´∀`*)←じこちゅぅ~
たしかに薬扱いでしたね~ ´∀`)
あれも、剣の珠を引き換えに渡してしまって
茶を持ち帰ったはいいものの母に泣いて茶を捨てられるというねw
先祖の品の剣の宝珠だったものだから…… という話で……^^;カンケイナイカ
まぁ、西暦200年頃でそうだったわけですから
もう少し前からありそうですよね~
嗜好に適する品々は大抵薬扱いですからね~
むしろ、今のほうが薬ではなく嗜好品扱いだとも言えますが~
コメント感謝です~^^
すごく興味深かったです♪
なんとなく、お茶って最初はお薬だっただろうなぁ…とは思っていたけど…
いろいろな観点がありますね~v(´∀`*)