孝道
- カテゴリ:自作小説
- 2015/01/27 11:42:09
「・・・」
「・・・お帰り、重蔵。」
孫の、”予想通りの”早過ぎる帰宅に対し、茂十はそれだけの声を掛けた。
それ以上、掛ける言葉は無かった。
「”小汚い痩せ百姓の分際で、由緒ある南田家の敷居を跨ぐとは身の程を弁えよ”だとさ。」
喪服代わりの黒い着物のまま、重蔵は我が家の床にごろりと手枕で寝転がった。
「その”小汚い痩せ百姓”の娘を孕ませやがったのは、何処のどなた様だってんだ。」
「・・・」
「ま、いいさ。」
重蔵は天井を眺めつつ、ぽつりと漏らした。
「父親ったって、顔もほとんど見た事ぁ無ぇ。世話んなった覚えも無ぇ。そんな野郎の葬式なんざ、出る義理も無ぇさ。頼まれたって願い下げだぃ。」
「・・・南田様は、何で亡くなったのじゃろうなぁ。」
「知らね。」
両脚を高く挙げ、勢いを付けて、重蔵が身を起こした。
「また、女中奉公の娘に手ぇ出そうとして、叩っ殺されたんだったりしてな。」
「重蔵。」
「それよりさ、爺さん。」
茂十の窘めを遮り、重蔵は快活に告げた。
「畑の雑草、早く取ろうぜ。この時期は伸びんの早ぇからな!」
何かを、吹っ切ろうとするかの如く。
「人として恥ずかしいとは思わぬか!この不孝者!」
三日後。
裃姿の若侍を引き連れた卑しからぬ身形の女は、重蔵の家にずかずかと上がり込むなり、一喝した。
「・・・はぁ?」
重蔵はその女が、自分を追い返した南田家の女である事を思い出す。
「下賤の者は魂から腐り切って居るのか!この畜生腹めが!」
「・・・何なんだよ一体。」
感情に任せた女の言葉は、全く要領を得なかった。
が、延々と喚き続けられた為に、その断片を繋ぎ合わせ、どうにか言い分を呑み込んだ。
どうやら、女は重蔵の父親であり、三千石の大身旗本家、南田家の当主であった南田主水輔忠継の妻、栄、であるらしい。
栄が言うには、主水輔は、山本仁之助と言う侍に”殺された”のだそうだ。
つまり、その仇を討つのは子として当然であり、それをしようとしない重蔵は親不孝だ、と、そう言う訳だ。
とは言う物の、重蔵自身、主水輔が殺害された事自体、初耳である。
そもそも、その経緯も語らず犬でも追う様に門前で踏ん張っていたのは、この栄自身なのだが、それも思慮の外にあるようだ。
「あ、あの、その、それは、つまりその・・・」
茂十が畏れ入りつつ、狼狽し、それでも勢い込むと言う、何とも複雑な様相で問う。
「し、重蔵を、南田の御殿様の子と、認めて頂けると言う・・・」
「無礼な!下賤の百姓が由緒ある南田家の末席に座ろう等と!身の程を弁えよ!」
「へ、へへぇっ!」
「・・・」
茂十は畏まってしまったが、重蔵は正直、呆れ返っていた。
子とは認めぬが、親不孝者。
矛盾以上に、滅茶苦茶だ。
「もう、良いでしょう。栄様。」
若侍が、ふ、と笑って口を開いた。
「犬畜生に、孝道を説いても所詮、解ろう筈も御座いません。」
「そう言う訳には参りませぬ!南田家の遺恨は、いくら汚れた血が混じった賤しい生まれでも、曲がりなりにも南田家の血を継いだ者の手で・・・!」
「しかし、野良犬に討たれる山本仁之助では・・・」
「・・・そう言うあんたは、女のケツを追っ掛けるしか能の無い、飼い犬かい?」
黙って聞いていたが、余りの言われ様に、重蔵の堪忍袋が切れた。
「な、何を無礼な!」
「そっちのあんたも、キャンキャン吠えて。まるで捨て犬だね。」
「ななな、何ですってぇっ!」
「お、おい重蔵!」
茂十が慌てて制止したが、もう重蔵は止まらない。
「百姓の娘に犬見てぇに盛って孕ませた野郎の嫁と家来だもんな。犬のその下って事かね。」
「こ、この!このぉ・・・!」
「きぃぃ!」
「何だい、歯ぁぎりぎり鳴らして。そんなにすると、欠けて餌ぁ食えなくなるぜ。」
「栄様!」
若侍、すっくと立ち上がる。
「やはり野良犬には、躾が必要のようですな!この、一刀流目録、酒井忠吾が、生意気な口ごと叩き伏せてやりましょう!」
「よろしい!やって御仕舞いなさいっ!身の程と言う物を教えてやりなさいっ!」
「おう。上等だ。表ぇ出ろ。」
重蔵と忠吾、二人は連れ立ち、庭へと出た。
「し、重蔵!」
茂十が泡を喰って外へ出ると、既に二人は対峙していた。
「さぁ野良犬。何処からでも来るがい・・・」
「おらぁっ!」
「ほげぇっ!?」
忠吾の言葉が終わらぬ内に、重蔵の拳が忠吾の右頬にめり込んだ。
「ひ、卑怯だぞ・・・!」
涙目の忠吾は、頬を押さえ、涙目のまま震える声で抗議した。
「か、構えも終わらぬ内にとは・・・!」
「・・・」
途中とは言え、何処からでも来いと言ったのは自分自身である事を、すっかり棚に上げている。
「や、やはり野良犬には作法と言う物が・・・!」
「もう一発やっか?」
「ひぃぃ!」
拳を振り上げる重蔵に対し、頭を抱えて蹲る忠吾。
重蔵は呆れるを通り越して、憐れになって来た。
「お、おお!腕前は不足無い様じゃ!」
栄が歓声を挙げる。
「これなら山本仁之助にも勝てようぞ!では、早速・・・」
「もう、いい加減にしてくれ。」
重蔵は溜息混じりに吐き捨てた。
「侍の事は、侍で決着付けてくれ。百姓を巻き込むな。」
「な、何を!お前、孝道と言う物を・・・!」
「解らねぇな。少なくとも、あんたの言う親孝行は、ね。」
「な!な!な!」
「何せ俺ぁ・・・」
重蔵は、栄に不敵な笑みを向けた。
「野良犬なもんでね。」
「・・・!」
栄は忠吾の尻を蹴り飛ばし、二人連れ立って、這う這うの態で帰って行った。
後に聞けば、山本仁之助は二百石の軽禄である事を主水輔に馬鹿にされ、その発言の撤回を要求し、しかしその申し出に更に揶揄を重ねられた事に腹を立て、脇差しの峰でぶん殴った、のだと言う。
それに怖気付いて詫びの手紙を書いていた所、あの栄にそれを見付かってしまい、散々怯懦を罵倒された上に、詫びる必要など無い、高々二百石の微禄の分際でと、油を注いだ火の様に騒ぎが大きくなりかけてしまった。
それに思い悩んだ末、元々気の小さい主水輔は首を括ったのだと言う。
その顛末を耳に入れた重蔵は、もう何を言っていいのか分からなくなってしまった。
今日も重蔵は、畑仕事に精を出す。
空を仰げば、雲雀が高く飛び、声を挙げていた。
[完]





















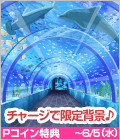





日本を支えて来たのは、百姓と職人だと、私は思うからです。