▽青の話―高貴なる青(2)
- カテゴリ:勉強
- 2011/01/25 22:42:35
どうもどうも。
コメントありがとうございました。
寄り道しても良いとの許可を頂きましたので、今回は高貴なる青の第二弾、「ブルーブラッド」について書こうかなぁと思います。
文字を直訳すると「青い血」。
お前の血は何色だー! とか、ブルーフレンドだ!とか、むしろ冷血漢か!恐怖の味噌汁か!と僕なんかは反応しちゃうけどまったく関係ございません。
be bone in the purpleが王侯の家に生まれるという意味と一緒。
blue bloodとなるとこれは貴族(もしくは名門)の血統という意味になる。
これは英語だけど、元はスペイン語のsangre azulです。
「Azulって単語、そう言えば何処かで聞いたなー」と思ったあなた。前回の記事をどうぞご参照くださいw
ま、当時の貴族は食生活が一般の農民階級と違ったからね。
まだ小麦の生産効率も良くなかった農民の食事はふすま麦とかの雑穀中心で、一方の貴族の食生活と言うとパン、林檎、肉などなど。
まぁ今見てもそれなりに贅沢だった訳です。
その食生活の差、というか栄養状態の差ゆえに、貴族たちは一般の人より若干青みがかった血の色になっていたってのがこの語の語源です。
……。
……。
……いや、真っ赤なウソですけどね。
昔学生時代に友人をひっかけようと言ってみた冗談を焼き直してみました。(見事にひっかかってくれて嬉しかったよ、B君)
はい、真面目にやります。
さて、時は8世紀。
当時のヨーロッパはイスラームの脅威に晒されてた。
レコンキスタ(国土回復運動)が始まったのもこの時代だけど、その前提としてイスラームがヨーロッパの方に相当侵略を進めてた背景があるんだよね。
実際イベリア半島は711年には西ゴートを滅ぼしたウマイヤ朝によって征服されてる。
で、このレコンキスタが活発化してって、イベリア半島にも大きなイスラームへの抵抗勢力が幾つか興って来る。
そのひとつが11世紀半ばに現れるカスティリア王国。
ブルーブラッドは実は、このカスティリア王国。追っ払われた元西ゴート王国の貴族の皆様が礎の王国ですな。
その貴族たちが、イスラームからやって来た異邦者達と比較した時に己の高貴さを示すものとして「青く血管の透ける白い肌」を挙げたのがsangre azulというわけ。
純血とか血の連帯感の意識が非常に強い彼ららしい言葉だね。
もう一つ、キリスト教において青が「希望」「敬虔」「誠実」等のイメージを冠されてるせいもあったんじゃないかなぁ?
なにせ、レコンキスタはキリスト教のカスティリア貴族とイスラームの戦いって面もアピールされてたしねぇ……ま、この辺は推測ってことで。
ちなみに、この青い血のネットワーク、ブルボン王朝とかにまで広がってて、今現在のヨーロッパ各国の王室、貴族等にまで綿々と続いてるそうな。
うーん、何と言うかさすが、なのかなぁ。
一方で、この考えがユダヤ人の迫害(向こうの目からするとユダヤ人の肌は黄色いらしい)なんかにも波及しているとか……。
今更だけど色の話って、宗教とか人種とか結構デリケートな所に絡んでくるんですよねぇ。
あまり深く話すと色々と問題になりそうだなぁ…;
歴史の流れはアバウトな説明だから突っ込まないでねw


















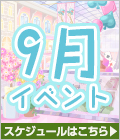









確かふし○発見だったかなぁ……。
絵画などにも当時のその化粧をしていた様子が描かれたものがあるとか。
昔は肌を白さを際立たせるためだだったか、
うっすら透けてる血管のうえを青鉛筆でなぞる化粧があったという話を読んだことがあります。
今の感覚では不健康そうな印象を与えるとしか思えないお化粧ですが、
なるほどこういう事情だったのかと納得しました。
ここからというよりもっと古い話ですねぇ。
色というのは非常に分かりやすい差別化ですから。
仏教の世界と言えば、だるまの色が赤いのは達磨大師が高僧であることの証だからだとか。
(仏教界では赤は高僧ですしねぇ)
一般の僕らの身近にも色による差別化ってのはあると思いますよ。
例えば柔道の黒帯とか。
ま、色々ですよねぇ。
色で格差をつけるのも
ここから始まっているのでしょうか
仏教の世界も
色分けされていたような?
まぁ 一般人の我々には
関係ないのでしょうが…