藍色の話 前編
- カテゴリ:勉強
- 2017/01/11 21:26:53
もう4、5年前のリクエストに応えて、今更ではあるのだけど藍色の話。
これでケルト青まで話を広げると僕の技量ではオーバーするので、日本限定で。
藍染の知識が日本に渡来したのが大体5世紀(応神~雄略)頃。
で、奈良時代には技法として確立していたとみられているそうな。
例えば、みんな大好き正倉院の中にも藍染作品がいくつも見られる。
縹地大唐花文錦残欠……簡単に言うと青地に花柄の琵琶袋とか、
開眼縷なんかも、かなり青いね。これは、大仏の開眼式に使われたものらしいね。
http://www.sachio-yoshioka.com/blog/2002/08/d26/
ああ、そうそう。
藍という植物が単品であるように想像しがちだけど、実際は違う。
藍染の材料になる植物は一種類だけじゃないし、
葉っぱから抽出するもの、茎から抽出するもの、草じゃなくて木からとる場合もある。
日本でも本州だと蓼藍(たであい)が主流だけど、沖縄に行けば琉球藍、北海道とか北の方では大青(たいせい)呼ばれる別の草が藍の原料になるしね。
インド藍はナンバンコマツナギが主な原料だ。
その地域で一番簡単に、大量に手に入る藍色素を含むもの。それが藍色を支えていた訳だね。
なお、ピュア・インディゴはコールタールが原料。インド藍を分析した結果生まれた人造藍だね。
藍から生まれる青色については、また別途。


















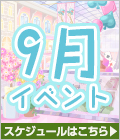









青系の色は好きですが、藍染の技術が奈良時代にはあった、というのは知りませんでした。
とても古い技術だったのですね。
虫除けの効能もこの頃には知られていたのでしょうか。
歴史にも思い馳せるとロマンがありますね☆(^^