藍色の話 後編
- カテゴリ:勉強
- 2017/01/12 00:22:11
染色において、染められる素体が動物線維か植物繊維かは大事な問題で、
染料によっては動物性(ウールとか)は染まるけど、植物性には定着しないとか、
逆に植物性の麻、綿は良くても、動物性の絹はダメだとか。
その点、藍はどっちもOKだから、使い勝手が良かったんだろうね。
紺屋の白袴、なんて諺ができるくらいだし、江戸時代の染色屋では藍色は主力商品だったのだろう。
おかげさまで藍染のバリエーションは豊かだ。
思いつくまま列挙してみよう。
藍色、縹、甕覗き、浅葱、褐色、紺、留紺、エトセトラ。
甕覗きは、ものすごくうすーい藍色。名前が洒落ているよね。
浅葱は新選組の羽織の色ということで有名だろうか。
褐色はかっしょく、ではなく「かちいろ」。黒に近い深い藍色だ。夜空の色だね。
個人的には好きな色だ。
上流階級というか武士の藍染は比較的明るい(薄い)青、澄んだ青の藍染、
藍建ての時に入れる木灰を厳選した上質な藍色を薄く建たせていた。
日本画の青が濃ければ濃い程高級とされたのとは正反対だね。
まあ、岩絵の具の青の原料になる瑠璃は、磨るほどに白っぽくなるから
濃い青=混じりけのない顔料を大量に消費=貴重! となるし、
一方、衣類の青は不労階級だから、汚れが目立たないように濃く染める必要が
無かったんだろうね。
庶民の青は、もっと濃い、木灰や石灰を入れて色落ちしづらい藍を作っていた。
西洋の庶民の青がペールブルーだった事を考えると、おもしろい対比だね。





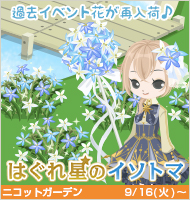












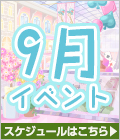









身分さと色の違いは調べだすと止まらなくなりますw
藍染は調べだすと想像以上に幅広くて驚きますよ。
ちなみに、藍染ではありませんが紅は「呉の藍(染料)→くれあい→くれない」から名前が来ていたり。
そこまで考えたことがなかったので興味深いです。
生え始めの葱の色が藍染から生まれていたなんて驚きです。
色にまつわる話が好きですね。
歴史は調べると面白いですよね。
歴史というのは面白いです