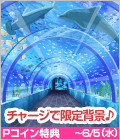side ジャムとヤマブキと旅人だった男・2
- カテゴリ:自作小説
- 2011/04/29 08:41:02
「ああごめんなさい。綺麗な顔をしてる人だなあ。って思って。」
笑顔でヤマブキが臆面もなくそう言うと、男は更に訝しげな表情を濃くしながらも、どうも。と頭を下げた。
「それ、俺は喜んでいいんですか?」
「喜んでいいんじゃないのかな。」
男の戸惑うような問いかけに、褒められたのならば素直に喜べばいいのに変なの。と微かに肩をすくめてヤマブキがそう言うと、ふ、と男は可笑しげに目元を綻ばせた。
「じゃあ、ありがとう。」
「どういたしまして。というか不躾な事を言って、礼を言われるとは思わなかったけど。」
そう言うと、不躾な事をしていたという自覚はあるんですか。と男は更に笑みを深くした。
「俺は、まさか初対面に外見を褒められるとは思っていなかったです。」
くつくつと笑いをこぼしながら男はそう言った。
そんなに面白い事を言った覚えは無いけれど。とヤマブキが男の言葉に首をかしげていると、お待たせしました。とアオイがコーヒーとトーストを持ってきてくれた。
二つに切り分けられた厚切りのトーストにコーヒー。そしてその脇には、まるでルビーの様に濃く艶やかな紅に染まった苺の粒が残る、とろりと甘そうな苺ジャムの入った小瓶が添えられている。
待望のものが目の前に差し出されて、満足げなため息をひとつ吐き、ヤマブキはトーストを手にした。表面がカリカリに焼けたまだ温かなその上に、瓶の中からほとんど苺の形が残っているジャムをスプーンで掬いあげて乗せる。ころりと苺が落ちて行かないように気をつけながら、それをほおばった。
さくさくと香ばしいトーストに、甘い苺の香りに味。そしてさわやかな酸味。柔らかくもプチプチとした食感が残る苺が口の中でとろんとゆるく溶けて、また素朴で優しい甘みが新たに広がっていく。
「美味しい」
猫のようににんまりと目を細めてヤマブキがそう言うと、アオイも又、心底嬉しそうに目元を綻ばせた。
「苺が、ちゃんと形のままで残っているのね。」
そう言いながらヤマブキがもう一口ほおばると、こくん、とアオイは頷いた。
「小さめの苺だったから、ヘタをとるだけで良かったんです。」
「へえ?いや市販のジャムって、こんな風に果肉が残っているものを見ないから。」
「そうなんですか?」
そう小首を傾げて、アオイはジャムはほとんど買った事がないんです。と付けくわえた。
「故郷では、姉さんが季節毎にいつも作ってたから。」
「すごいお姉さんね。」
ジャムなんて作った事のないヤマブキはその言葉に、目をぱちくりと瞬かせた。
驚いているヤマブキに、簡単なんですよ。とアオイは微笑んだ。
なんにしろ、そのお姉さんのお陰でアオイはジャムを作れるようになったみたいだ。お姉さん様々だわ。なんて事を思いながら、ヤマブキは再びもう一口、イチゴ丸ごとのジャムのトーストをほおばり、美味しい。とにまにまと笑った。
と、ふと視線を感じでヤマブキが顔を上げると、先ほどの男がどこか面白そうな表情でヤマブキを見つめてきていた。
「何?」
もぐもぐと、口の中のトーストを飲みこんでからヤマブキが問うと、美味しそうに食べるなあ。と思って。と男は笑顔で言った。
「本当にすごく楽しみにしていたんですね。」
そう面白そうにいう男に、まあね。とヤマブキが意味もなく胸を張ると、男は何が可笑しいのか更に破顔した。