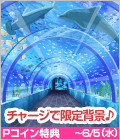side 観測者・2
- カテゴリ:自作小説
- 2011/05/31 22:18:24
「サハラよ、若いお姉ちゃんに今日手紙を渡されていなかったか?」
「そうそう、サハラ君が席に近づくと顔を真っ赤にする子もいたな。可愛らしいものだ」
「よりどりみどりだなぁ」
うけけけけ。と心の底から面白がっている笑い声を上げながら、懇意にしている親父たちがからかってくる。
こういう事をサハラが苦手にしているのを親父たちは知っているのだから、余計にたちが悪い。いい加減イラッと来たので、ここで飲み過ぎている事、奥さん達に言いますよ。と言ってやった。
「親父さん達がここで一杯と言わず二杯も三倍もビールを飲んでいる事を、おかみさん達に言いますよ」
やり返したサハラに、おぅ。それは言わないでくれ。と親父たちは情けない声を上げた。
「モテモテなのに不機嫌なんて、勿体ないわね」
そんな彼らの傍に、くすくすと笑いながらカスミがグラスを持って近づいてきた。
そもそもカスミがあんな事を言わなければ、女の子たちに騒がれる事もなかったかもしれない。と、面白がるカスミに向けて思わずじとりとした視線をサハラは向けた。
サハラがこの店の手伝いをするにあたって、当初は普段着にエプロンをつけるだけ恰好で働く予定だった。だがしかし、普段通りのジーンズにTシャツ姿で現れたサハラに、丁度店にいたカスミが、どうせならばパリッとした格好をすればいいのに。と言ったのだ。
「サハラさんは端正な顔をしているのだから。こう、白シャツに黒いギャルソンエプロンを巻いて。で、黒いタイでも巻けばかなり格好良くなると思うのよね」
その言葉にアオイが、それじゃあ。と白いシャツやらギャルソンエプロンやらを買ってきてくれたのだ。ネクタイは堅苦しくて苦手なのだけど、そこまでされて着ないわけにもいかなかったので、渡されたまま着用して働き。
結果。なんだかぱりっとした格好の、格好良いお兄さんが給仕をしてくれる。とそんな話が流れてしまったのだ。
「私はアドバイスしただけだもん。恐ろしく似合ってしまったのは私のせいじゃないわ」
と、サハラの視線にカスミは肩をすくめた。
「いいじゃない。アオイちゃんもお客さんが増えて喜んでいるわけだし」
「そうそう。むしろモテて何で喜ばないんだ。って話だが」
「ああ、もしかして。サハラ君には既に好きな子でも居るのか?」
だからモテても嬉しくないんだな。と親父たちがまたもやサハラを肴に沸き立つ。その様子にサハラは、いませんよ。と再びため息をついた。
「いません。というか、そういうのは面倒なんです」
ばっさりと。そうサハラは切り捨てた。
「面白くない奴だなぁ」
「俺も一度でいいからモテモテの状態で、そういうの興味ない。とか言ってみたいものだ」
「お前はどの面でそんな事を言うんだ」
「少なくともお前よりは男前だと思っているが」
気が付くと、親父たちの会話が違う方向に向かってくれた事にほっとしながら、サハラはそこから離れて開いたグラスをカウンターの向こうに運んだ。
色んな土地を流れている中で、浮いた話が無かったわけではない。よれよれした雰囲気の、けれど良く見ると格好良いサハラにちょっかいを出してくる女はそれなりにいたし、サハラも女性の扱いにはそれなりに経験はあった。
けれど、根なし草の自分をひたむきに追いかけてくるような女の子はいなかった。だからこそ、戸惑いを感じてしまうのだ。
真っ直ぐに愛情をかけられても、同じだけのものを返す事が出来ない。なかなかどうして薄情な人間だな。と自分でも思うが。
今は、サハラはこの場に留まる事を選んではいる。けれど。自分はいつ、またこの街を出て旅に出るか分からない人間だよ。と、可愛らしく頬を染めて熱い眼差しを向けられると、そう言いたくなる自分がいるのだ。
誰かとの繋がりがこの身を縛る事を心地よく感じても。それでも誰かに束縛されない自由を欲する自分が消えたわけではないから。
そう。自分は特定の誰かを幸せにする事なんか、きっとできない。