ゲゲゲの鬼太郎の原点
- カテゴリ:アニメ
- 2017/09/10 22:33:33
ゲゲゲの鬼太郎
ゲゲゲの鬼太郎の原点は、1933年から1935年頃にかけて、民話の『子育て幽霊』を脚色した『ハカバキタロー(墓場奇太郎)』(原作:伊藤正美、作画:辰巳恵洋)という紙芝居が存在しており、『黄金バット』をも凌ぐほどの人気だった。
1954年、紙芝居の貸元である阪神画劇社と紙芝居作者として契約していた水木は、同社社長・鈴木勝丸に前述のハカバキタローを題材にした作品を描くよう勧められた。
作者承諾の上で、水木はオリジナルの紙芝居『蛇人』『空手鬼太郎』『ガロア』『幽霊の手』の4作を仕立てたのが鬼太郎シリーズの原点となったのです。
漫画作品は貸本を経て1965年から1997年の間に数多くのシリーズが描かれ、幼年誌から青年誌まで幅広く掲載され、連載当初のタイトルは『墓場の鬼太郎』であったものがアニメ化に伴い改題されて、怪奇色の強かった内容も鬼太郎と妖怪の対決路線へと変化して鬼太郎は正義のヒーローとしての側面が強くなっていったといわれています。
そして、「ゲゲゲ」の由来は水木が幼い頃に自分の名前を「しげる」と言えずに「ゲゲル」「ゲゲ」と言っていたことから着想したもので、妖怪ブームを巻き起こしたテレビアニメは日本のテレビアニメ史上最多となるシリーズ5作、4回のリバイバルを果たしたのです。
ですが奇抜な展開で評判を呼んだ『空手鬼太郎』を除いては、鬼太郎シリーズはそれほど人気は出なかったためにそれ以降は製作されず、この水木版紙芝居の鬼太郎作品は現存しないが伊藤版の一部は加太こうじの『紙芝居昭和史』などの書籍で部分的に見ることが出来ます。
ちなみに鬼太郎が墓場から生まれた片目の子供という設定(『蛇人』より)と目玉おやじの登場(『空手鬼太郎』より)はこの頃からで、貸本漫画家に転身した水木は1960年に兎月書房発行の怪奇短編マンガ誌『妖奇伝』に「幽霊一家」を発表し、ここで現在の鬼太郎の基礎が定まったのですが、この時期の鬼太郎はまだ人間の味方ではなく関わった人々に怪奇な結末をもたらす不吉な少年という位置づけでした。
そして、『妖奇伝』第2号には第2作「幽霊一家 墓場鬼太郎」が掲載されたのですが、『妖奇伝』は一般には全く人気が出ず廃刊になったのです。
ただし、鬼太郎シリーズは熱心な読者からのファンレターがあり、同年に同じく兎月書房から『墓場鬼太郎』と題した怪奇短編マンガ誌上で「地獄の片道切符」(第1巻)「下宿屋」(第2巻)「あう時はいつも死人」(第3巻)などのシリーズ諸作が発表され、「下宿屋」ではねずみ男がシリーズに初登場したのです。
また、水木は兎月書房の専属に近い形だったのが経営難の兎月書房からは原稿料が一切支払われなくなつたことから憤慨した水木は長井勝一の三洋社に移籍し、『鬼太郎夜話』シリーズ「吸血木と猫娘」「地獄の散歩道」「水神様が町にやってきた」「顔の中の敵」を順次発表し、以前に書いた「幽霊一家」から「顔の中の敵」までは一連の物語になり、後年『ガロ』版「鬼太郎の誕生」及び「鬼太郎夜話」としてリメイクされたのです。
しかし、5冊目「カメ男の巻」を出す段階で三洋社の社長が入院したために、そのドサクサで原稿が行方不明となり「カメ男の巻」は幻の作品となってしまった一方で、兎月書房は『墓場鬼太郎』の続編を竹内寛行に切り換えて中断した『墓場鬼太郎』を4巻から19巻まで書き継がせ、やがて水木は兎月書房と和解して1962年には読切作品『怪奇一番勝負』『霧の中のジョニー』を描くこととなったのです。
しかしその後は兎月書房も倒産し、水木は1964年に佐藤プロで読み切り作品『おかしな奴』、『ボクは新入生』、『アホな男』を発行したのですが、しかし売れ行きが伸びず佐藤プロは鬼太郎シリーズの刊行を断念したそうです。
桜井昌一の東考社が後を引き継ぎ『霧の中のジョニー』の続編と予定されていた『ないしょの話』を発行し、鬼太郎はこの頃には後の少年誌に登場する親しみやすいキャラクターへと変貌したようです。
(Wikipedia参考)





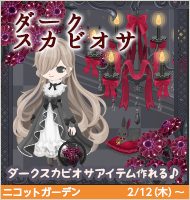























今回のこのイベントを通じて鬼太郎の色々な事を
知ることが出来ましたよ。(*^_^*)
子供の頃に見たアニメの印象が強いです^^;