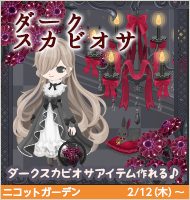薬に頼らず食事で病気を予防 No.1
- カテゴリ:美容/健康
- 2019/12/01 21:10:44
薬に頼らず食事で病気を予防 人気漢方店店主が教える症状別食材と食べ方
( 介護ポストセブン2019/12/01 11:30 )
最近、グッと冷え込みが厳しくなり、体調をくずしやすい季節になった。
薬をのむほどじゃないけれど、なんとなく調子が悪い──そんな時は、食べ物で体調を整えてみてはいかがだろうか。
「いつもの食材も、食べ方次第で薬の代わりになるんです」とは、人気漢方店店主の櫻井大典さん。
今年の冬は、食べて“養生”してみませんか?
飽食の時代──私たちは日々たくさんの食べ物を口にし、それにより、体がつくられている。
この当たり前のことを意識し、今の体に必要な食材や食べ方を考えて食事を摂る人は意外に少ない。
「例えば、寒い季節にのどが渇いたからと氷水を一気飲みしたらお腹を壊しやすくなります。
しかし、温めて飲めば、渇きは癒えるし、体も温まりますよね。このように、“食べ方”は重要なんです」
そう教えてくれたのは、北海道で漢方店を営みつつ、漢方の理論をやさしく伝える“ゆるゆる漢方家”櫻井大典さんだ。
「私の専門である漢方では、食事を最も大切にしています。体調が悪いからといってすぐ薬をのむのではなく、原因を見極めて、問題を解決するための食材と食べ方を選びます。食べることで根本的な治療を目指しているのです」(櫻井さん・以下同)
5つの味の5つの効果
●鹹味(かんみ)
・硬いものをやわらかくする。
塩辛い味のこと。水分代謝を高めるので、便秘の改善やリンパ腺の腫れなどに効果的。
・摂るべき人:老化が気になる人。尿の出が気になる人。
・注意点:摂り過ぎると、血がドロドロになりやすく、心臓や血管系疾患のリスクが高まる。
・適した食材:豚肉、あさり、しじみ、はまぐり、いか、かき、昆布、わかめなど。
●辛み
・配や呼吸器を強化し発汗を促す。
肺の働きを活性化し、発汗を促す。
血行も促進させるので、肩こりや冷えなどにも効果的。
・摂るべき人:冷え性の人、気分が落ち込みがちな人
・注意点:摂り過ぎると、筋がひきつりやすくなったり、爪がかけやすくなる。
・適した食材:にら、ねぎ、玉ねぎ、にんにく、しょうが、しそ、とうがらし、こしょうなど。
●甘味
・胃腸の働きを助け緊張をゆるめる
砂糖由来以外の甘味には、滋養強壮効果が。消化器系の働きをよくし、痛みを和らげる。
・摂るべき人:疲労感が抜けない人、食欲不振の人。
・注意点:摂りすぎると胃腸や骨が弱り。髪が抜けやすくなる。
・適した食材:米、大豆、鶏肉、鮭、にんじん、さつまいも、かぼちゃ、バナナなど。
●苦味
・体内の余分な水分を取り、炎症をしずめる。
体にたまった余分な水分や老廃物を取り、おもった熱を冷ます。神経を鎮静させる作用も。
・摂るべき人:ほてりやのぼせなどの症状がある人。
・注意点:摂りすぎると、乾燥したり、体を冷やすことも。
・適した食材:苦うり、レタス、アスパラガス、みょうが、ぎんなん、緑茶など。
●酸味
・自律神経を整えて水分の排出を抑える。
自律神経を整え、汗や尿、便が必要以上に出ないように抑える作用がある。
・摂るべき人:お腹をよくくだす人、目をよく使う人。
・注意点:摂りすぎると胃を弱め、筋肉を萎縮させることもある。
・適した食材:梅、レモン、みかん、りんご、いちご、トマト、酢、ローズヒップなど。
漢方の考え方によると、すべての食材には、それぞれ独自の働きがあるという。
「食材には5つの味(五味)があり、それぞれ、体への影響が異なります。
例えば、甘味のある食材には胃腸の働きを助ける作用があり、辛味のある食材には発汗を促して、血流をよくする働きがあります」(詳細は上記表参照)
今、自分の体は何を欲しがっているのかを常に意識し、忙しくても食べることをおろそかにしてはいけない。
甘いものが欲しい時は消化器系が弱っていたりと、体はちゃんと、訴えてくれるのだから。
「油っぽくて味が濃いものや甘いものを控え、温かい食事を摂ることも大切」と櫻井さん。
難しく考えない、ゆる~い“食養生”。今日から実践してみよう。
症状に合わせた養生レシピ
ここからは、症状に合わせた養生レシピをご紹介する。
※レシピはすべて1人分。電子レンジの加熱時間は600Wの場合。500Wの場合は2割増し、700Wの場合は2割減に。
発熱の時の養生レシピ
熱っぽかったり、のどの痛みがある風邪を、漢方の世界では“赤い風邪”という。
対策としては、余分な熱を取ること。ミント(ハッカ)には、発汗作用や解熱作用があるので、活用してみよう。
市販のティーバッグタイプでいれた温かい「ミントティー」がおすすめだ。
<作り方>
ミントティーは温かい湯でいれる。
アイスティーにするとお腹が冷えて不調のもとになる。
ほかにもこんな食材が
■りんご
体にたまった余分な熱を冷まして、潤いを与える効果が。
胃腸の働きを整える働きもあり。
■れんこん
熱っぽさやのどの痛みなどの炎症をしずめて、潤いを補う力がある。
(豆知識)
漢方というと、「風邪なら葛根湯」と考えがちだが、これは間違い。熱症状(熱感、のどの痛み、渇きなど)がある時にのむと悪化することもあるので、服用には注意が必要。漢方の専門家の指示を仰ぐこと。
咳が出る時の養生レシピ
風邪が長引いて咳が出ることを、漢方の世界では“乾いた風邪”という。
このタイプの風邪は、加湿と保温が肝心。
ただし、発汗させるのはNG。汗が出ると体内が余計に乾燥してしまうからだ。
おすすめは「蒸し梨」。梨には渇きや乾燥を癒す作用がある。
<作り方>
梨のヘタ部分を横に切り、芯をくり抜く。
そこに氷砂糖3~4粒と水を大さじ1、生のしょうがスライスを1枚入れて40~50分蒸す。
時間がない場合は、梨を一口大に切って電子レンジで約3分加熱するだけでもよい。
ほかにもこんな食材が
■ゆり根
潤いを補給する作用のある食材で、生薬としても使われている。
■梅
肺の機能を回復させて、咳を止める働きがある。
梅シロップで摂るのがおすすめ。
(豆知識)
ゆり根は調理が難しい。1枚ずつはがしてアルミ箔に包み、蒸し焼きに