夢飼い。【17】
- カテゴリ:自作小説
- 2013/01/23 23:33:41
Story - 2 / 6
諦め、哀れみ、悲しみ。
それは誰に抱いている思いなのか、僕にはもうわからない。
いくら乾に〝帰ってきてくれ〟と願ったところで、そこにいるのは紛れも無く乾でしかない。
それは悲しいことなのか。
だって、乾は。乾であって、乾でしかない。
たとえどんなにその性格が変わろうと捻じ曲がろうと寝たきりになろうと僕の事を忘れてしまっても。
僕は結局、乾に何を伝えたかったんだろう。
好きだと、言いたかったのか。
……いや、違う。
僕はただ、届かなくても良いと勝手に一方通行しながらずっと、思っていた。
高校に上がって、独りぼっちで寂しそうにしているから近づいてみた。
特に友達なんて作る気の無かった僕は、その相手が異性だからって大して気にしないで接していた。
最初は変なヤツ、もとい、鬱陶しがられていたような気がする。
一年経ってクラスが変わらなかったからずっと一緒に居ただけの、恋人未満友達以上。
お互いにどうとか思っているわけじゃなくて、ただ〝傍に居れば良い〟と感じていた。
徐々に心を開いてくれた気難しい女の子は、厨ニ病の代表っぽく「自分が嫌い」だ、といつか僕に漏らしてくれた。
その言葉が嘘か嘘じゃないかなんてどうでも良かった。
ただ、その言葉が初めて僕に見せてくれた本心だったような気がして。
嬉しかった。
その場の出任せでも良い、本音だったら、って。
信じるとか信じないとか、そんなこともどうでも良い。
所詮僕らは、まだまだ子供なんだから。
裏切って裏切られて、傷つけて傷ついて。
それで、血を流したって。
それで、道を踏み外したって。
僕は良いと思っていた。
それがその人の生き方だ。
僕の知ったことじゃないし、ほら。
結局は、他人事だ。
みんなみんな、知らないうちに溜め込んだ傍観者思考のままに生きている。
ありきたりな不幸ほど、ラノベで読めば安っぽく。己が身に降り掛かれば悲劇のヒロインになれる。
人は死んだらどこに行くか、考えるのにも飽きてきて。
僕はやっぱり周りで見知った人物が死んでも実感が沸かなかった。
死ぬってなんだ。
生命活動が停止すること?みんなの目から見えなくなること?
――わからない。
わからなくていい、と思っていた。
――布団の中でかすんだ意識が思考を一人走りさせていた。
あれから家に帰って、またベッドにもぐりこんでいた。
宿題も出されてなんているわけがなくて、脳裏には乾の、呆けたような笑顔が焼きついていた。
甘ったるい声が鼓膜にこびり付いて、たまに幻聴した。
――ゆき、
僕を呼ぶ声が。
どうしようもなく普段の乾に重ならなくて。
また乾に逢いに行くのが怖かった。
明日行きますなんて言っておいて、行く勇気なんてこれっぽっちも無くなっていた。
どうしたら良い。僕は、どんな顔をして乾と逢えば良い。傍に居てあげれば良い。
でも、目を離すのも怖くなって。
結局明日になったら性懲りもなく病院に行く為に自転車を漕いでるんだろうな――僕はいつの間にか眠っていた。
*
翌朝。
なんだか、寝てばかりのような気がする。
起きて、適当にご飯を食べて、病院に行って、帰ってきたらまた寝て。
そうして気が向いたように風呂は朝に入って――自分でもげんなりするほど不摂生だった。
でも。
それでも懲りずに、僕はまた病院に行く。
まるで書きたくも無い誓約書に間違ってサインしてしまったかのように、律儀に乾に逢いに行くんだ。
悲しくなるのは僕なのに。
正直言ってもう泣きたかった。
泣いたけど。
*
すっかり通り慣れた、もとい歩き慣れた廊下を早足に。
昨日もだけど、例のあの自動ドアはどうしてか開いていて僕は勝手に侵入しているも同然だった。
未紗さんか虎崎さんが開けてくれたんだと考えるのが一番合理的だしありそうだけど、
まだ自分から言い出してお礼を口にする気には至れていない。
「こんにちは」
午前11時20分過ぎ。
スライド式のドアを開け、口にした挨拶に返ってくる言葉はなかった。
代わりに、聴こえたのは小さなうめき声。
ベッドに真っ直ぐ向けていた視線を床に落とすと、
僕の足のほうに必死に手を伸ばしてもがく乾が
泡を吹いて「あー」とか「うー」とか不明瞭な声を発していた。
点滴のチューブが腕から外れて、無理やり引っこ抜かれた長い針が
生白い腕に紅い線を描いている。
血は出ていないけれど、見ているだけで痛々しい。
「な……、ど、」
――どうしよう。
当然のように僕はたじろいだ。
というか戸惑った。驚いた。もとい。
今更っぽく床に倒れる乾に駆け寄る。
長い爪で病院の床を引っ掻く手つきは弱弱しくて、目は虚ろだった。
眼鏡がテレビの台に置いてある。
起きてすぐにベッドから這い出してこうなったんだろうか。
病室から出たかったのか、単にトイレに行きたかっただけなのか判別ができない。
ただ、今はまともな精神状態じゃないことだけはわかった。
床を這う両手を取って、突いた膝に乾の上半身を引き上げるように引っ張って抱き寄せた。
驚くほど冷たい手。
抱き寄せた身体は小刻みに震えていた。
それが痙攣しているんだと気づいたら、見計らったように乾がむせた。
酸素を取り込もうとして、引き攣った喉が鳴る。
水気交じりの咳を繰り返すごとに僕の胸の辺りによだれと泡っぽいものが吐き出されて、
無意識に乾の背中を撫でていた。
人って本当に泡吹くんだ、なんて場違いなことを考えつつ、早く助けを呼ばないといけないと辺りを見回した僕の視界にナースコールのボタンが見切れる。
くそ、遠い……!
ベッドの枕元にあるボタンまで、どう見積もっても5歩は必要だった。
まずい。
乾の痙攣が不自然に大きくなったり、咳の隙間の下手くそな呼吸が、器官をひどく苦しそうに喘息っぽくぜろぜろ言わせている。
乾を放ってボタンを押しに行くべきか、乾を抱いて歩けるか考える。
――どちらにしたってさっさと動けば良いものを、僕は何も出来ないでいた。
そして焦りのままにショート寸前の頭の中に響く、
「由貴くん?」
珍しく心配そうな、深刻そうな虎崎さんの声。
小走りに近寄ってくるのがわかって、僕はそれだけでひどく安心してしまった。
同時に、自分の無力さに失望した。
案の定僕はあわてる。
「ッ虎崎さん、乾が、泡、泡吹いて、倒れてて――」
「わかってます」
――落ち着いて。
もういいから、どけ、と言われた気がした。
僕の単語を並べた意味不明な訴えで全てを理解したらしい虎崎さんは、
僕の腕の中から乾を掬い上げるように抱き上げて、素早くベッドに寝かせた。
宙を掻く乾の手が虎崎さんの小さな背中の向こうに見える。
虎崎さんはポケットから小さな注射器を取り出した。
その乾の手をぱっと捕まえて、薬剤を打ち込むまで、鮮やかな仕事に言葉を失うほかない。
どんな顔をしていようと、曲がりなりにもこの人は看護士だった。
ぴく、と震える乾の全身から力が抜ける。
おまけのように口許を拭いてやるのが見えて、布団を掛けなおす虎崎さんをどこか遠くに見た。
もういやだ。
その注射器の中に入っていた薬の名前も訊きたくない。
乾は、可笑しくなってしまった。
*****
望んだこと、絶したこと。
思いだけが空回り。
――ここまでお付き合いいただいた、画面の向こうのあなたに精一杯の感謝を。
今後の大いなる励みに、お読みいただいた方に感想等いただければ、幸いです。
-糾蝶-





















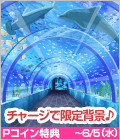




コメント感謝です*
ふふふ、これからますます歪んでいきます……!笑
お楽しみ頂ければ幸いです、頑張ります故!
ハッピーエンドになるのかそれともバッドエンドになるのか…
どちらにせよ私の薄っぺらい脳では予想がつきません(^o^三^o^)