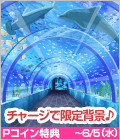ツーショット その1
- カテゴリ:自作小説
- 2015/06/03 21:57:46
「はい、撮りま~す。笑って~」とカメラマンがシャッターを切る修学旅行の集合写真の順番が、いよいよわたしのクラスの番に近づいてきた。
どうしよう、すごいドキドキする…
別にわたしが写真に写るのが恥ずかしいというわけじゃない。確かに前に出て目立とうということが得意というわけじゃないんだけど。
問題はただ一つ。
集合写真でわたしが、タダシ君のとなりに並んで写ることができるかということ。それだけ。
タダシ君はわたしが片想いしてる相手だ。
集合写真をととる時間なんてほんの一瞬に過ぎないんだけど、二泊三日の修学旅行の中のこの瞬間のためだけに、わたしは自分の全てをかけようとしている…
タダシ君と出会ったのは、クラス替えで一緒になった去年の中学二年の春のことだった。
わたしのとなりの席にいたのがタダシ君だった。
タダシ君はとなりの席で友達と楽しそうにおしゃべりしてよく笑う男の子だったけど、元々ひっこみじあんで男の子を自然と避けるような性格のわたしにとっては、最初苦手な存在でしかなかった。
わたしはとなりのタダシ君に対して心の垣根を作っていたんだけど、タダシ君はその心の垣根をあっという間に飛び越えてきてしまった。
きっかけは授業中忘れた教科書を見せてあげたとかごくありふれた事だったんだけれども、そんなありふれたことに対してタダシ君はとびっきりの笑顔で返してきたのだ。
笑顔で気兼ねなく接してくれるタダシ君に対して、わたしが打ち解けていくのにそう時間はかからなかった。
やがて席替えでタダシ君と席は離れてしまうのだけれど、わたしは自然とタダシ君の後ろ姿を追うようになっていた。
その時はまだちょっと気になる存在だったという、それくらいの気持ちだったと思う。
タダシくんへの気持ちが恋心だってことに気付いたのはその夏休み前の下校時のことだった。
わたしはブラスバンド部でタダシ君は剣道部と違う部活だったから、下校時間が重なることはほとんどない。
だけれどその日、ブラスバンド部の練習を終えて校舎を出たわたしは、もう日が暮れかかっているのにもかかわらず、未だ電気が灯って運動部の練習音が響く体育館がふと気になって、中をのぞいたのだ。中ではタダシ君がいる剣道部がまだ稽古を続けている。
稽古で竹刀を構えるタダシ君は、わたしが普段目で追ってる昼間とは正反対の姿だった。タダシ君の周りだけ空気が張り詰めていて、その真剣な目つきはまるで吸い込まれてしまいそうになる…
結局その姿に見惚れて練習の最後までのぞいてしまった。
そのあとタダシ君と目が合ってそのまま一緒に並んで歩いた帰り道で、「昼の教室での雰囲気との違うのでびっくりした。」って尋ねたらタダシ君はこう答えた。
「自分は器用な性格じゃないから、中途半端にならないようにしてるだけなんだ。」
一見違うように見えるけど、そのどちらも決して手を抜かないで一生懸命に物事に取り組んでるタダシ君を、素敵だなって思った。
そのときわたしはタダシ君のことが好きだって初めて思ったんだ。
誰かを好きになることでそれまで何てことなかった世界が色鮮やかに見えるってことを聞いたことがあるけど、それってホントのことなんだ。
学校への登校だって大好きなタダシ君に会えると思うと足が自然に軽くなるし、その後長い夏休みがはじまってタダシ君と会う時間がますますなくなるってことに気が沈んだりと、日々の小さな出来事に一喜一憂している状態になった。
まったく、恋は人を盲目にさせるとはよく言ったものだなあと思う。
夏休みが明けてまた普通の学校生活が始まると、授業の後の部活の練習が早く終わった時なんかはきまってタダシ君のいる体育館の剣道部の練習をのぞき見していたし、練習が終わってタダシ君が帰る頃を見計らって「わたしも今部活が終わったところ」と鉢合わせを装って一緒に帰ったりすることもあった。
学校から二人で一緒に帰る時間なんてたかだか十数分程度だけども、タダシ君と二人で帰る時間がわたしにとって一番幸せな時間だ。
もしわたしに犬みたいな尻尾が付いていたらタダシ君に向かってぶんぶん振っていたと思う。そう考えて、ああ私は犬じゃなくて良かった、もしそうなら私のタダシ君への思いが筒抜けだもの…と真剣に考えてハッとしてそう考えてる自分に呆れて…
それでも別れる時は、このたった十数分の帰り道がいつまでも続けばいいのにといつも名残惜しくなるわけで…
中学3年に上がった時のクラス替えの時も同じクラスの名簿にタダシ君の名前を見つけた時は心の中で躍り上がっていたのを今でも思い出す。
タダシ君が好き。
タダシ君のことを考えてるだけで胸かしめつけられ切なく苦しくなる、だけどそれが何かとてもあったかくて心地よい不思議な気持ちにいつもさせてくれるのだ。
多分それはとても幸せなことなんだと思う。
「…それはそうなんだけどさ、あんたそれだけタダシ君のことが好きなのに結局タダシ君に告白はしないの?」
中学三年に上がってしばらく経った頃、気兼ねなく相談に乗ってくれる友達のサエがわたしにそう尋ねた。
「…だって告白してもし断られたら?それを考えるだけでわたし怖いよ。」
「とてもいつも部活を覗いて一緒に帰るのを待つ人間の言うこととは思えないわね。でもいい?わたしたちはもう中3なの。受験生なのよ。卒業してしまったらそれっきりになってしまうかもしれないのよ。あんたそれでもいいわけ?」
そうなのだ。今まで考えないようにしてたけど、タダシ君と確実に一緒にいられるのはあと1年もないのだ。今までだってクラス替えの時一緒のクラスになれるかどうかでおっかなびっくりしていたわけで…それにいずれ来てしまうタイムリミットを考えるとそれだけで胸が張り裂けそうになってしまいそうだ。
「でも…」
「告白もせず卒業してしまったら絶対にあと先悔いを残すと思うよ。それに見ているだけでは欲しいものはいつまでたっても手に入らないものなんだよ。」
なお躊躇するわたしにサエは諭すように言った。
そんなことはわかっているのだけれど…
-
- みかさ
- 2015/06/04 19:14
- ありがとうございます(^-^)
-

- 違反申告
-
- 大潮
- 2015/06/04 17:39
- 胸キュンだね
-

- 違反申告
-
- 奈柚
- 2015/06/03 22:51
- 初々しいね(^-^*)
-

- 違反申告